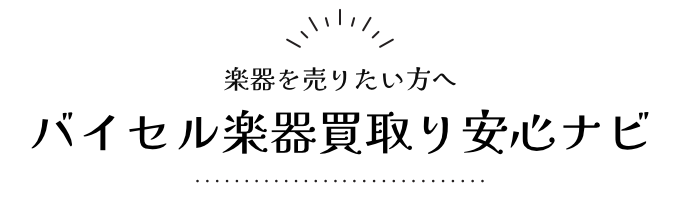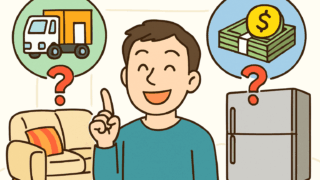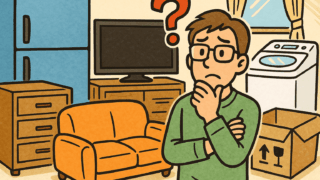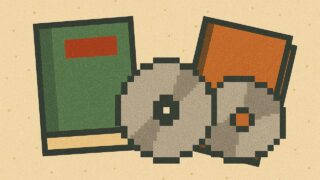使わなくなった楽器、家のスペースを取っているし、そろそろ手放そうかな…。
今、こんな風に悩んでいる方も多いかもしれませんね。
そして、そういう時に真っ先に思い浮かべる売却方法が、「メルカリ」や「ヤフオク」といった、いわゆる「フリマアプリ」なんじゃないかと思います。
たしかに、スマホ一つで簡単に出品できるイメージがありますし、「うまくいけば、お店に売るよりずっと高く売れるかも?」なんていう期待もありますよね。
でも、ちょっと待ってください。
実は、「楽器」という大きくてデリケートな商品をフリマアプリで売ろうとすると、洋服や本、ゲームソフトを売るのとはワケが違う、本当に「致命的」とも言えるような落とし穴が、いくつも待っているんです。
「え、ギターの梱包ってどうやるの?」
「送料や手数料を引いたら、結局手元にいくら残るんだろう?」
「もし配送中に壊れたら、誰が責任をとるの?」
こうした具体的な不安を抱えている方もいれば、中には「まあ、なんとかなるでしょ!」と、あまり深く考えずに始めようとしている方もいるかもしれません。
ここでは、そんなフリマアプリで楽器を売る際の「メリット」と、それ以上にあなたが知っておくべき「リアルなデメリット(特に梱包・送料・手数料の問題)」を、徹底的に解説していきます。
そして、その全ての面倒やリスクを回避できる、もっと「賢い手放し方」についても、詳しくご紹介していきますね。
楽器を手放してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、ぜひ最後までじっくりと読んでみてください。
メルカリ・ヤフオクで楽器を売るメリットとは?

使わなくなった楽器をどうしようか考えた時、真っ先にメルカリやヤフオクといったフリマアプリを思い浮かべる人は多いと思います。
たしかに、スマホ一つで簡単に出品できて、うまくいけば高く売れるかもしれないというのは、すごく魅力的に聞こえますよね。
ここでは、まずフリマアプリで楽器を売る場合の「良いところ」、つまりメリットについて整理してみたいと思います。
どんな方法にも良い面と悪い面がありますから、まずはポジティブな側面からしっかりチェックしていきましょう。
もしかしたら、あなたの楽器や状況にとっては、フリマアプリがベストな選択になるかもしれませんしね。
主なメリットとしては、価格の自由度や手軽さ、利用者の多さなどが挙げられる感じがします。
順番に見ていきましょう。
自分で価格を決められる(高く売れる可能性)
フリマアプリを使う最大のメリットは、やっぱり「自分で価格を決められる」ことだと思います。
楽器買取サービスにお願いすると、査定額は基本的にお店側が決めますよね。
もちろんプロの目で見てくれる安心感はありますが、「本当はもう少し高く売りたいんだけどな…」と感じることもあるかもしれません。
その点、フリマアプリなら「この価格なら手放してもいい」という自分の希望額で出品できます。
もし、その楽器の市場での人気が高かったり、状態がすごく良かったりすれば、一般的な買取相場よりもずっと高い価格で売れる可能性も秘めているわけです。
いわゆる「言い値」でスタートできるのは、売り手にとって大きな魅力ですよね。
ただし、もちろん、その価格で売れるかどうかは別の話です。
高すぎれば誰も買ってくれませんし、安すぎれば自分が損をしてしまいます。
だから、事前に「同じ楽器がいくらで売れているか」をしっかりリサーチする手間は必要になる、という点は覚えておきたいところです。
それでも、価格決定の主導権が自分にあるというのは、とても大きなメリットだと私は思います。
スマホひとつで出品できる手軽さ
もう一つの大きなメリットは、その「手軽さ」ですね。
今やほとんどの人がスマホを持っていると思いますが、そのスマホさえあれば、誰でも簡単に出品できてしまいます。
具体的には、売りたい楽器の写真をスマホで何枚か撮って、楽器の状態や特徴を説明する文章を入力して、価格を決めて、出品ボタンをタップするだけ。
本当にこれだけで、日本中の人に向けて「この楽器買いませんか?」とアピールできるわけです。
お店に重い楽器を持っていく必要もありませんし、査定の予約をする必要もありません。
自宅の部屋で、自分の好きなタイミングで作業できるのは、忙しい現代人にとってすごく合っているスタイルだと思います。
メルカリやヤフオクのアプリも、操作がとても分かりやすく作られていますよね。
普段からSNSやネットショッピングを使っている人なら、迷うことなく出品作業ができるはずです。
この「思い立ったらすぐ行動できる」というスピード感と手軽さは、フリマアプリならではの強みだと感じます。
利用者が多く、見てもらえる機会が多い
メルカリやヤフオクって、本当にたくさんの人が利用していますよね。
テレビCMもよく見かけますし、日常的に「メルカリで買った」とか「ヤフオクで探してる」なんて会話も耳にします。
このように利用者が圧倒的に多いプラットフォームに出品するということは、それだけ自分の楽器が多くの人の目に触れるチャンスがある、ということです。
例えば、近所のリサイクルショップに置いてもらうだけでは、そのお店に来る人にしか見てもらえません。
でも、フリマアプリなら、北は北海道から南は沖縄まで、日本中の「楽器が欲しい人」が検索対象になるわけです。
見てもらえる回数(いわゆるインプレッションですね)が多ければ多いほど、当然ながら「買いたい」と言ってくれる人が現れる確率も高まります。
特に、フェンダーやギブソン、ヤマハといった人気メーカーの定番モデルや、状態の良い楽器であれば、出品して割とすぐに「いいね!」がついたり、購入希望のコメントが入ったりすることも珍しくありません。
この「集客力の強さ」は、個人でモノを売る上ですごく大きなアドバンテージだと思います。
ニッチな楽器でも欲しい人が見つかるかも?
メリットの4つ目として、ちょっとマニアックな楽器でも買い手が見つかる可能性がある、という点が挙げられます。
例えば、すごく古いビンテージのエフェクターとか、今はもう製造されていないメーカーのパーツとか、あるいは民族楽器のようなちょっと特殊なものとか。
こういう楽器って、一般的な楽器買取店に持っていくと、「うちでは扱えません」と断られたり、ほとんど値段がつかなかったりすることがあるんですよね。
お店側も、それを買い取った後に売れる見込みがないと、なかなか高値はつけられませんから。
でも、フリマアプリには、本当に色々な趣味やニーズを持った人が集まっています。
世間一般には需要がなくても、「まさにそのエフェクターを探してた!」「このパーツがどうしても必要だった!」という熱心なコレクターやマニアな方が、日本中のどこかにいるかもしれないんです。
そうした人と個人間で直接つながれるのが、フリマアプリの面白いところであり、大きなメリットだと感じます。
お店では価値ゼロと判断されたものでも、欲しい人にとっては「お宝」かもしれませんからね。
フリマアプリの販売プロセス(出品から入金まで)
最後に、フリマアプリで売買が成立した時の、大まかな流れについても確認しておきましょう。
メリットというよりは、仕組みの紹介になりますが、全体像を知っておくのは大事なことだと思います。
まず、ステップ1は「出品」です。
これは先ほどお話しした通り、写真と説明文を用意してアプリから登録することですね。
ステップ2は「コメント対応」。
出品すると、「もう少し安くなりませんか?」という値下げ交渉や、「この部分の写真を追加してください」といった質問がコメントで来ることがあります。
これに対応するのも出品者の役目です。
ステップ3で、価格や条件に納得した人が「購入ボタン」を押すと、売買成立です。
ステップ4は「梱包・発送」。
売れた楽器を、配送中に壊れないように丁寧に梱包して、購入者に発送します。
ステップ5は「受取・評価」。
商品が無事に購入者の元に届いたら、購入者が中身を確認して「受け取りました」という評価をします。
そして最後のステップ6が「入金」です。
購入者の評価が終わると、フリマアプリの運営から、送料や手数料を引いた金額が「売上金」としてアカウントに入金されます。
この売上金を自分の銀行口座に振り込んでもらう手続き(振込申請)をして、ようやく現金として手元に入る、という流れですね。
こうして見ると、出品して終わりではなく、売れた後にも結構やることがあるんだな、という感じがしませんか?
要注意!メルカリ・ヤフオクで楽器を売る際の「致命的なデメリット」

さて、前の章ではフリマアプリの良いところ、つまりメリットを見てきました。
たしかに魅力的な部分も多いのですが、物事には必ず裏表がありますよね。
特に「楽器」という、大きくてデリケートで、専門知識も必要なものを個人間で売買するとなると、服や本を売るのとは比べ物にならないほどの困難やリスクが潜んでいるんです。
ここでは、メインキーワード(検索意図)である「梱包」「送料」「手数料」の問題を中心に、フリマアプリで楽器を売る際に覚悟しておかなければならない、「致命的」とも言えるデメリットについて、しっかり掘り下げていきたいと思います。
良い面だけを見て「簡単そう!」と始めてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねませんからね。
ここはしっかり現実を見ていきましょう。
想像以上に大変!楽器の「梱包」という高いハードル
フリマアプリで楽器を売却しようとした人が、まず最初にぶつかる壁。
それが、メインキーワードの一つでもある「梱包」の問題だと思います。
正直なところ、これを経験した多くの人が「もう二度とやりたくない」と感じるほど、楽器の梱包は想像を絶する大変さなんですよね。
なぜそんなに大変なのか?
それは、楽器が「大きくて特殊な形」であり、かつ「非常にデリケートで壊れやすい」という特性を持っているからです。
洋服ならビニール袋に入れて紙袋に入れるだけでも大丈夫かもしれませんが、楽器はそうはいきません。
少しの衝撃でネックが折れたり、ボディにヒビが入ったりする可能性があるため、配送中に絶対に壊れないように、厳重すぎるほどの梱包が求められるわけです。
この「梱包」という高いハードルについて、もう少し具体的に見ていきましょう。
ギターやベースなど大型楽器の梱包資材はどうする?
例えば、ギターやベースを売ろうと思ったとします。
まず問題になるのが、「それを入れるダンボールをどうするか?」です。
あんなに細長くて大きなものが入るダンボールって、普通に生活していたら家にないですよね。
考えられる方法としては、楽器屋さんに頼んで、新しい楽器が入荷した時に出た空き箱(ダンボール)を運良く譲ってもらう、という手があります。
ただ、タイミングよく在庫があるとは限りませんし、あったとしてもお店から家まで持って帰るのも一苦労です。
もう一つの方法は、インターネット通販などで「ギター発送用ダンボール」を購入することです。
これは確実ですが、ダンボールと緩衝材のセットで、安くても1,500円、高いものだと3,000円くらいかかることもあります。
売上からこの費用が引かれると思うと、結構痛い出費ですよね。
最終手段として、スーパーなどでもらってきた複数のダンボールを、自分で切ったり貼ったりして「自作」する方法もありますが…。
これは本当に手間がかかりますし、素人が作った梱包では強度も心配です。
さらに、楽器本体を包むための緩衝材(プチプチやエアクッション)も、大量に必要になります。
ホームセンターで買うと、これも意外と高くつくんですよね。
このように、梱包資材を「揃える」というスタート地点だけでも、かなりの手間とコストがかかるのが現実です。
配送中に破損?トラブル時の責任問題
そして、楽器の梱包で最も恐ろしいのが、「配送中の破損」リスクです。
どんなに丁寧に梱包したつもりでも、配送業者のトラックの中で荷物が揺れたり、他の荷物の下敷きになったりして、不慮の事故が起こる可能性はゼロではありません。
もし購入者の元に届いた時に、ネックが折れていたり、ボディにヒビが入っていたりしたら…想像するだけでもゾッとしますよね。
購入者からは当然、「壊れているから返品したい」「返金してほしい」という連絡が来ます。
ここで問題になるのが、「責任の所在」です。
それは「出品者(あなた)の梱包が不十分だった」のが原因なのか、それとも「配送業者の取り扱いが悪かった」のが原因なのか、はたまた「購入者が開封時に壊した」のか…。
この判断は非常に難しく、当事者間での話し合いは泥沼化しやすいんです。
フリマアプリの運営や配送業者が提供する補償制度もありますが、申請の手続きは煩雑です。
特に、運営側から「梱包が不十分だったと判断される」場合、補償の対象外となってしまい、売上金も入らず、壊れた楽器だけが手元に戻ってくる(あるいは返品送料まで負担する)という、最悪の事態も考えられるようです。
この精神的ストレスは、本当に計り知れないものがあると思います。
エフェクターなど小型楽器でも梱包は手間がかかる
「なるほど、ギターみたいな大きい楽器が大変なのはわかった。
でも、手のひらサイズのエフェクターくらいなら簡単でしょ?」と思うかもしれません。
たしかに、サイズ的な問題はクリアしやすいです。
でも、忘れてはいけないのが、エフェクターも「精密機器」だということです。
見た目は頑丈な金属の箱でも、内部には繊細な基盤が入っていますし、表面には折れやすいツマミ(ノブ)がたくさん付いていますよね。
これらを適当な袋に入れて送ってしまうと、配送中の衝撃でツマミが根元から折れたり、内部のハンダが割れて音が出なくなったりする可能性があります。
ですから、小型楽器であっても、一つ一つ丁寧にプチプチで何重にも包み、さらにダンボール箱の中で商品がガタガタ動かないように、隙間なく緩衝材(丸めた新聞紙などでも代用できますが)を詰める必要があります。
もし商品の元箱(オリジナルの箱)が残っていれば、それが一番の梱包材になりますが、ない場合は、ちょうどいいサイズのダンボール箱を探す手間もかかります。
小さいからといって梱包の手間がゼロになるわけではなく、やはり気を使う作業であることには変わりないんですよね。
利益を圧迫する「送料」と「手数料」の罠
さて、なんとか大変な梱包作業が終わったとしましょう。
次なるデメリットは、メインキーワードでもある「送料」と「手数料」です。
これは、フリマアプリでモノを売る以上、避けては通れないコストですよね。
問題は、楽器の場合、この「送料」が特に高額になりがちだ、ということです。
そして、売れた金額がそのまま手元に入るわけではなく、そこから「手数料」もしっかり引かれます。
この2つのコストを甘く見積もっていると、「あれ?売れたのに、手元にこれだけしか残らないの?」と、ガッカリしてしまう「罠」にはまることになるんです。
ここも詳しく見ていきましょう。
大型楽器の送料はいくら?サイズ別料金の目安
読者の方が一番知りたい情報の一つが、この「送料」だと思います。
特にギターやベース、電子ピアノ、大型のキーボードなどは、梱包すると荷物の3辺(縦・横・高さ)の合計サイズが、通常の宅配便の上限である「160サイズ」や「170サイズ」を簡単に超えてしまいます。
例えば、ギターをダンボールに入れた場合、180サイズや200サイズになることも珍しくありません。
こうなると、まず送料が跳ね上がります。
ヤマト運輸の「ヤマト便(※現在は廃止され、大型荷物は宅急便のサイズ扱いか、ヤマトホームコンビニエンス扱いになります)」や佐川急便の「飛脚ラージサイズ宅配便」、ゆうパックの「重量ゆうパック」などを利用することになりますが、発送する地域から受け取る地域までの距離にもよりますが、安くても2,500円、遠方だと4,000円や5,000円といった送料がかかることも普通です。
さらに重要な注意点があります。
それは、メルカリの「らくらくメルカリ便」や「ゆうゆうメルカリ便」といった、安価で便利な「匿名配送」サービスが、一定のサイズ(執筆時点では160サイズや170サイズが上限のようです)を超えると利用できなくなることです。
匿名配送が使えないということは、お互いの氏名・住所・電話番号を知らせ合った上で、通常の宅配便(もちろん送料は出品者負担が基本)で発送しなければならない、ということ。
これは、個人情報を知られたくない人にとっては、かなりのデメリットですよね。
意外と痛い!フリマアプリの販売手数料(10%前後)
送料と並んで、確実に利益を削っていくのが「販売手数料」です。
メルカリやヤフオクなどの主要なフリマアプリでは、商品が売れた際、その販売価格に対して一律で「10%」程度(※サービスやキャンペーンによって変動することもあります)の手数料が差し引かれる仕組みになっています。
例えば、あなたの楽器が50,000円で売れたとしましょう。
その瞬間、フリマアプリの運営会社に「5,000円」を手数料として支払うことが確定します。
100,000円で売れたら、10,000円です。
「たかが10%」と思うかもしれませんが、こうして具体的な金額にしてみると、かなり大きな額だということがお分かりいただけると思います。
お店を持たずに場所を借りている「場所代(ショバ代)」のようなものだと考えれば仕方ないのかもしれませんが、この手数料の存在を忘れて「5万円で売れた、ラッキー!」と喜んでいると、後で売上金を見た時に「あれ?」となってしまうわけです。
販売価格を決める際は、この10%が引かれることを前提に値付けをしないと、自分が想定していた手取り額を大きく下回ってしまうので、本当に注意が必要ですね。
手元に残る金額はいくら?シミュレーションしてみよう
では、ここで一度、実際にフリマアプリで楽器が売れた場合、手元にいくら残るのかを具体的にシミュレーションしてみましょう。
例えば、あなたが「販売価格 30,000円」でギターを出品し、無事に売れたと仮定します。
まず、ここから「販売手数料(10%)」が引かれます。
30,000円 × 10% = 3,000円 ですね。
次に、発送にかかった「送料」が引かれます。
仮に大型サイズ扱いで、送料が 2,800円 だったとしましょう。
さらに、忘れてはいけないのが、梱包に使った「梱包資材費」です。
専用ダンボールと緩衝材をネットで買い、合計 1,500円 かかったとします。
さあ、計算してみましょう。
販売価格 30,000円 – 販売手数料 3,000円 – 送料 2,800円 – 梱包資材費 1,500円 = 22,700円。
どうでしょうか?
30,000円で売れたはずなのに、実際の手取り(利益)は 22,700円 という結果になりました。
実に7,300円もの金額が、諸経費として消えてしまったわけです。
もし送料がもっと高かったり、梱包資材にもっとお金がかかっていたりすれば、手取りはさらに減ります。
これが、フリマアプリの「手数料」と「送料」の恐ろしさ、利益を圧迫する「罠」の正体なんですね。
面倒な「個人間取引」のストレス
デメリットは、こうした目に見える「お金(コスト)」の問題だけではありません。
フリマアプリは、あくまで「個人」と「個人」が直接やり取りするプラットフォームです。
お店を介さない分、自由度が高い反面、すべてのコミュニケーションやトラブル対応を自分一人でこなさなければならない、という「手間」と「精神的ストレス」が発生します。
これが意外と厄介で、「お金の問題より、こっちの方がキツい」と感じる人も少なくないようです。
具体的にどんなストレスがあるのか、見てみましょう。
値下げ交渉や質問コメントへの対応
フリマアプリ、特にメルカリなどでは、「値下げ交渉」がもはや文化のようになっていますよね。
出品してすぐに「コメント失礼します。
〇〇円で即決させていただけないでしょうか?」といった交渉が入ることは日常茶飯事です。
「この価格で売りたい」と思って出品しているのに、こうした交渉コメントが来るたびに、「いくらまでなら下げようか…」「いや、断ろうか…」と悩み、返信を考えるのは、結構なストレスだと感じます。
また、楽器の出品となると、専門的な質問が飛んでくることも多いです。
「ネックの反り具合は、順反りですか?逆反りですか?」「トラスロッドは、締める方向・緩める方向どちらにも余裕がありますか?」「アンプに繋いだ時、ボリュームやトーンにガリノイズは出ませんか?」などなど…。
自分が楽器に詳しく、状態を正確に把握していれば答えられますが、もし知識がない場合、どう答えていいか困ってしまいますよね。
曖昧な返事をしたり、間違った情報を伝えてしまったりすると、それが後々のクレームの原因にもなりかねません。
こうしたコメント対応に、一日何度も時間を取られることもあります。
購入者とのやり取り(連絡、発送通知など)
無事に商品が売れた後も、やることは終わりではありません。
むしろ、ここからが本番とも言えます。
購入ボタンが押されたら、まずは「ご購入ありがとうございます。
発送準備に入りますので、今しばらくお待ちください」といったお礼と状況報告のメッセージを送るのが一般的です。
そして、梱包作業が完了し、発送の手配ができたら、「お待たせしております。
本日〇〇(配送業者名)にて発送いたしました。
追跡番号はxxxxです。
到着まで今しばらくお待ちください」といった発送完了の連絡を入れます。
こうした、いわゆる「こまめな連絡(報・連・相)」が、お互いに顔の見えない個人間取引では非常に重要になってくるんですね。
もちろん、中には無言で取引を進める人もいますが、多くの場合、こうした丁寧なコミュニケーションが求められます。
こういうマメな作業が元々好きな人ならいいのですが、苦手な人にとっては、かなりの負担になると思います。
相手によっては返信が全くなかったり、逆に「まだ発送されませんか?」と急かしてきたりと、色々な人がいるのも事実です。
クレームや返品要求への対応リスク
個人間取引における最大のストレスが、これかもしれません。
「クレーム対応」と「返品要求」のリスクです。
商品が無事に購入者の元に届き、「受け取り評価」をしてもらって、ようやく取引完了となります。
しかし、その前に購入者から「商品が説明文と違う」という連絡が入る可能性があります。
「説明になかった傷や打痕がある」「アンプに繋いでも音が出ない」「ノイズがひどくて使えない」「思っていた色と違った」など、クレームの内容は様々です。
もちろん、こちらに非(説明不足や確認漏れ)があれば、謝罪し、返品や返金(あるいは一部返金)に応じるなど、誠実な対応が必要です。
問題は、こちらに非がないと思われるケースや、購入者の主観(「思ったより弾きにくい」など)によるクレーム、あるいは非常に細かい(重箱の隅をつつくような)指摘の場合です。
中には、故意に商品を壊して返品を要求したり、すり替えたりする悪質なケースも、残念ながらゼロではないようです。
こうしたトラブルが発生した場合、フリマアプリの運営が間に入ってくれることもありますが、基本的には当事者間での話し合いが求められます。
こうした stressful なやり取りを、すべて自分一人で背負い込まなければならない可能性がある、というのは、大きなデメリットですよね。
専門知識がないと適正価格がわからない
前の章のメリットで、「自分で価格を決められる」という点を挙げました。
これは、裏を返せば「自分で適正な価格を判断できなければならない」というデメリットにもなるんです。
もし、あなたが売りたい楽器の「中古市場での相場」を全く知らなかったら、どうやって価格を決めますか?
例えば、親戚から譲り受けた古いギターがあったとします。
自分には価値がわからないからと、とりあえず「10,000円」で出品したとしましょう。
もしそれが、実は数十万円の価値がある貴重なビンテージギターだったら…?
あなたは相場を知らないばかりに、大損をしてしまうことになります。
逆に、自分が新品で5万円で買ったギターだからと、「3万円」くらいで出品したとします。
でも、市場では同じモデルがもっと安く(例えば1万5千円くらいで)取引されているとしたら、あなたの3万円のギターは高すぎて、誰からも見向きもされず、永遠に売れ残ってしまうかもしれません。
このように、楽器に関する専門知識や相場観がないと、「適正な価格設定」が非常に難しいんです。
フリマアプリで他の人がいくらで出品しているかをリサーチする方法もありますが、それも「売れ残っている価格」なのか「適正価格」なのかを見極める目が必要ですよね。
この「値付けの難しさ」は、特に楽器初心者の方にとっては、大きなリスクでありデメリットだと思います。
売れるまでの保管場所と時間コスト
最後のデメリットとして、意外と見落としがちな「保管場所」と「時間コスト」の問題を挙げておきたいと思います。
フリマアプリに出品したからといって、その楽器が次の日、あるいは1週間以内に売れるとは限りません。
特に高額なものや、ニッチな楽器であれば、買い手が見つかるまでに数ヶ月かかることも普通です。
その間、あなたはその楽器をどこに保管しておきますか?
ギターやベース、キーボードといった大型の楽器は、ソフトケースやハードケースに入れた状態でも、かなりのスペースを取りますよね。
部屋の隅に立てかけておくにしても邪魔になりますし、クローゼットや押し入れも圧迫します。
家族がいる方なら、「これ、いつ売れるの?邪魔なんだけど」と、冷たい視線を浴びることになるかもしれません。
また、売れるまでの間、あなたは常に出品したアプリのことを気にかけていなければなりません。
「いいね!」は付いたか?コメントは来ていないか?他の人の出品価格は変動していないか?など、定期的にチェックし、必要なら価格を下げたり、説明文を修正したりといった「メンテナンス」も必要です。
こうした「売れるまで待機している時間」と「その間にかかる手間(時間コスト)」、そして「場所を占有されるコスト」も、目には見えにくいですが、確実に存在するデメリットなんですね。
デメリットだけじゃない!フリマアプリで楽器が「売れない」理由

さて、前の章では、フリマアプリで楽器が「売れた後」に待ち受けている、梱包や送料、手数料、そして個人間トラブルといった、数々の「致命的なデメリット」について詳しく見てきました。
正直、「うわぁ、思ったよりずっと大変そうだな…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
でも、実はフリマアプリの厳しさはそれだけではないんです。
もう一つの大きな問題、それはメインキーワードの一つでもある「そもそも売れない」というリスクです。
どんなに頑張って写真を撮り、説明文を書いて出品しても、誰からも見向きもされず、何ヶ月も「いいね!」すらつかない…なんてことも、残念ながら珍しくありません。
ここでは、なぜフリマアプリで楽器が「売れない」のか、その主な理由について考えてみたいと思います。
これもまた、フリマアプリのシビアな現実なんですよね。
相場より高すぎる価格設定
楽器が売れない最も大きな理由、それはもう単純に「価格設定が高すぎる」ことです。
前の章でも少し触れましたが、楽器の専門知識や中古市場の相場観がないと、適正な価格をつけるのは本当に難しいんです。
「自分は新品で10万円で買ったから、まだキレイだし7万円くらいで売りたいな」と思う気持ちは、すごくよくわかります。
でも、もし市場でのその楽器の中古相場が「4万円」だとしたら、7万円で出品しても、誰も買ってはくれませんよね。
フリマアプリを利用している購入者は、非常にシビアに価格を比較検討しています。
同じ商品が他の人によってもっと安く出品されていたり、中古楽器店の販売価格とあまり変わらなかったりすれば、あえて個人(あなた)から買う理由はなくなってしまいます。
「少しでも高く売りたい」という出品者の希望と、「少しでも安く買いたい」という購入者の希望がマッチしない限り、売買は成立しないわけです。
この「値付けの失敗」が、売れ残り地獄の入り口になる一番の原因だと私は思います。
写真や説明文が魅力的ではない
次に売れない理由として挙げられるのが、「出品ページが魅力的ではない」ことです。
フリマアプリは、インターネット上のお店みたいなものです。
購入者は、実物の楽器を手に取って見ることはできません。
判断材料は、そこに掲載されている「写真」と「説明文」だけなんです。
例えば、写真がどうでしょうか?
部屋が暗くて楽器の色がよくわからなかったり、ピンボケしていたり、全体像が写っておらず一部しか見えなかったり…。
あるいは、楽器の「キズ」や「汚れ」といった、購入者が知りたいマイナスポイントを意図的に隠しているように見える写真もダメですよね。
こういうページを見た購入者は、「なんだか怪しいな」「状態が悪いのかな」と不安になり、すぐに別の出品ページに移ってしまいます。
説明文も同じです。
「使わなくなったので売ります」の一言だけでは、情報が少なすぎます。
いつ頃買ったのか、どのくらい使ったのか、音はちゃんと出るのか、ネックの反りやフレットの減り具合はどうなのか、付属品は何があるのか…。
こうした楽器特有の重要な情報が具体的に書かれていないと、購入者は怖くて購入ボタンを押せないんです。
逆に、専門用語を並べ立てただけの分かりにくい説明文も、初心者の方からは敬遠されてしまうかもしれません。
この「写真」と「説明文」で、いかに楽器の魅力を伝え、同時に購入者の不安を取り除けるかが、フリマアプリで売るための鍵になるんですね。
出品のタイミングや季節が悪い?
これは少しオカルト的な話に聞こえるかもしれませんが、意外と「出品するタイミング」も影響していることがあるようです。
例えば、楽器というのは、一般的に新生活が始まる春(4月前後)や、ボーナス時期(夏・冬)などに需要が高まる傾向がある、と言われています。
学生さんが部活やサークルで始めたり、社会人の方が趣味で新しい楽器を買ったりする時期ですね。
逆に、ゴールデンウィークやお盆、年末年始といった大型連休中は、みんなレジャーや帰省でお金を使ったり、忙しくしたりしていて、高額な楽器のチェックは後回しにされがちかもしれません。
また、フリマアプリは、毎日とんでもない数の商品が新しく出品されています。
あなたが出品した楽器も、数時間後にはタイムライン(新着一覧)のはるか下に埋もれてしまい、誰の目にも止まらなくなっている可能性があります。
そのため、多くの人がスマホをチェックするであろう「平日の夜」や「週末の午後」などを狙って出品したり、売れない場合は一度出品を取り下げて「再出品」したり、といった工夫が必要になることもあります。
こういう地道な作業も、結構な手間ですよね。
競合(他の出品者)が多すぎる
もし、あなたが売りたい楽器が、非常に人気のある「定番モデル」だった場合も、注意が必要です。
例えば、スクワイヤやフェンダージャパンのストラトキャスター、BOSSの定番エフェクター(DS-1やBD-2など)、ヤマハの入門用アコースティックギターなど…。
こうした楽器は、「欲しい!」と思う人が多いのと同時に、「売りたい!」と思って出品しているライバル(競合)も非常に多いんです。
購入者は、フリマアプリ内でその型番を検索し、ずらっと並んだ出品リストの中から、「最も状態が良くて、最も安いもの」を選ぼうとします。
仮にあなたが15,000円で出品していたとして、ほぼ同じ状態で14,900円で出品しているライバルがいたら、そちらが先に売れてしまう可能性が高いですよね。
この厳しい「価格競争」に巻き込まれてしまうと、売るためには自分の価格をどんどん下げていくしかありません。
その結果、「値下げ交渉」と「ライバルとの競争」に消耗してしまい、結局、自分が思っていたよりもずっと安い金額で手放すことになってしまう…というのも、よくあるパターンだと思います。
そもそも需要がない楽器(状態が悪いなど)
最後に、これが一番根本的な理由かもしれませんが、「その楽器自体に、中古市場での需要がほとんどない」という可能性です。
メリットの章で「ニッチな楽器でも欲しい人が見つかるかも?」と書きましたが、あれはどちらかというと稀なラッキーケースです。
現実的には、元々の新品価格が非常に安い(例えば1万円以下の)入門用セットの楽器や、今はもう誰も知らないような無名メーカーの楽器は、中古になっても欲しいという人が少ないのが実情です。
また、楽器としての「状態」も非常に重要です。
見た目はキレイでも、ネックが大きく反ってしまっていて弦高が異常に高い(弾きにくい)とか、アンプに繋いでも音が出たり出なかったりする(電装系に不具合がある)とか、フレットがすり減りすぎて音がビビる(要修理)とか…。
こうした「ジャンク品」に近い状態の楽器は、自分で修理できる上級者や、部品取りが目的の人以外は、まず買いません。
購入者も「安物買いの銭失い」はしたくないですからね。
よほどタダ同然の価格で出すか、「ジャンク品・部品取りに」と明記しない限り、状態の悪い楽器がフリマアプリで売れるのは難しい、と考えた方が良いでしょう。
フリマアプリのデメリットを回避!「楽器買取サービス」という賢い選択

さて、前の章までで、フリマアプリで楽器を売る際の「致命的なデメリット」と、そもそも「売れない」理由について、かなり詳しく見てきました。
「梱包って、そんなに資材が要るの…」「送料と手数料で、手取りがそんなに減っちゃうの?」「配送中の破損や、購入者とのトラブル…考えただけで胃が痛い…」「そもそも売れなかったら、あの苦労は全部ムダ…?」
今、こんな風に感じて、フリマアプリに出品するのをためらってしまっている方も多いのではないでしょうか。
「じゃあ、この弾かなくなった楽器、どうしたらいいのよ!」と思いますよね。
ご安心ください。
まさに、そうしたフリマアプリの「面倒くささ」や「リスク」を、すべてまとめて解決してくれる「賢い選択肢」があるんです。
それが、この記事の本題でもある「楽器買取サービス(楽器専門の買取業者)」を利用する方法です。
ここでは、なぜ楽器買取サービスがフリマアプリのデメリットを回避できるのか、その理由を具体的に見ていきましょう。
面倒な「梱包」や「発送」が不要なケースが多い
フリマアプリで楽器を売る際の、最大のハードルは「梱包」と「発送」でしたよね。
特にギターやベース、キーボードなどの大型楽器は、梱包資材を揃えるだけでも一苦労で、送料もかさむ…。
この一番面倒な部分を、楽器買取サービスは劇的に楽にしてくれるんです。
買取方法にはいくつか種類がありますが、特に「出張買取」というサービスに対応している業者さんなら、なんと、スタッフの方が直接あなたの自宅まで来てくれます。
そして、その場で楽器の状態を見て査定額を提示し、あなたがその金額に納得すれば、その場で現金(または振込)で支払い、そして…ここが重要ですが、「梱包一切不要」で、そのままスタッフの方が楽器を運び出してくれるんです。
すごくないですか?
あなたは文字通り、家で待っているだけでいいんです。
あの、ダンボールを探し回ったり、プチプチを大量に買ったり、配送業者とサイズで揉めたり…といった苦労が、すべて「ゼロ」になります。
これは、大型楽器を売りたい人にとっては、本当に信じられないくらい大きなメリットだと思います。
また、近くにお店がない方向けの「宅配買取」という方法でも、多くのサービスが「無料の梱包キット(ダンボールや緩衝材、送り状など)」を自宅まで送ってくれます。
あなたは、その送られてきたダンボールに楽器を入れて(もちろん、この梱包作業は必要ですが、資材を探す手間はありません)、配送業者に電話して「集荷」に来てもらうだけ。
自分でコンビニや営業所に重い楽器を持っていく必要すらないんです。
フリマアプリの梱包・発送の手間と比べたら、天と地ほどの差があると言っても過言ではないと私は思います。
「送料」や「手数料」が無料のサービスも
フリマアプリで利益を圧迫する、もう一つの大きな要因が「手数料(約10%)」と「高額な送料」でした。
売上が3万円でも、手取りは2万3千円弱になってしまう…というシミュレーションは、結構衝撃的でしたよね。
この点についても、楽器買取サービスは非常に明快です。
多くの(というか、ほとんどのまともな)楽器買取サービスでは、これらの費用が「無料」に設定されています。
まず、「宅配買取」で楽器を送る際の「送料」は、業者が負担してくれます(着払い用の送り状が送られてくるか、後で精算してくれます)。
もちろん「出張買取」なら、スタッフの方の出張費や運搬費も無料です。
そして、フリマアプリの「販売手数料10%」のような、よくわからない手数料は一切かかりません。
さらに、「査定料(楽器を見て値段をつける費用)」や、査定額をあなたの銀行口座に振り込む際の「振込手数料」まで、すべて無料というサービスが主流です。
これはつまり、業者から提示された「査定額 30,000円」にあなたが納得すれば、その「30,000円」が、そのまま満額あなたの手元に入る(振り込まれる)ということです。
「ここから送料と手数料が引かれて…」なんていう、面倒な引き算をする必要は一切ありません。
提示された金額が、そのまま手取り額になる。
この「わかりやすさ」と「安心感」は、フリマアプリにはない、非常に大きなメリットですよね。
プロが査定するから適正価格がわかる安心感
フリマアプリでは、「自分の楽器の適正な相場がわからない」という悩みがありました。
価値ある楽器を安すぎに出品して損をしたり、逆に高すぎて誰にも見向きもされなかったり…というリスクです。
この点も、楽器買取サービスなら心配ありません。
なぜなら、査定をしてくれるのは、日々たくさんの楽器を扱い、中古市場の動向を熟知している「楽器のプロ」だからです。
あなたの大切にしてきた楽器が、どのメーカーの、いつ頃のモデルで、現在の状態はどうか、そして「今の中古市場」ではどれくらいの価値があるのかを、専門知識に基づいて客観的に判断してくれます。
もしかしたら、自分では「こんなの売れないだろう」と思っていた古いエフェクターや、少し壊れているジャンク品でも、プロの目から見れば「修理すれば使える」とか「このパーツに価値がある」と判断され、値段がつくこともあります。
逆に、フリマアプリで「10万円で売れるかも!」と夢見ていたものが、実際には「相場は5万円ですね」と現実的な価格を提示されることもあるでしょう。
でも、それは「騙されている」のではなく、それが「今の適正な市場価値」なんです。
その「客観的な答え」を知ることができるだけでも、大きな価値があると思いませんか?
相場を知らないが故に大損をするリスクを完全に回避できるのは、プロに任せる最大のメリットの一つです。
個人間トラブルの心配が一切ない
そして、私がフリマアプリの最大のデメリットだと感じている「精神的ストレス」。
しつこい値下げ交渉、専門的な質問への対応、そして何より怖いのが、売った「後」に購入者から来るクレームや返品要求…。
こうした「個人間取引」ならではのトラブルの心配が、楽器買取サービスなら「一切ない」と言い切れます。
なぜなら、あなたの取引相手は、顔も名前も知らない「どこかの個人」ではなく、「楽器店」という「企業(法人)」だからです。
査定額が提示され、あなたが「その金額でお願いします」と承諾し、楽器を引き渡した(または宅配買取で了承の連絡をした)時点で、その取引は「完全」に「終了」します。
その後に、お店側から「やっぱりここに傷があったから返金してくれ」とか「音が思ったのと違ったから返品します」なんていう連絡が来ることは、絶対にありません。
(もしそんなことを言う業者がいたら、それはもう悪徳業者なので絶対に関わってはいけません。)
査定額に納得がいかなければ、「今回はやめておきます」と断ることも自由です(※宅配買取での返送料がかかるかは、次の章で説明しますね)。
あの、フリマアプリで売れた後の「ちゃんと届くかな…」「クレームが来ないかな…」という、独特のドキドキやストレスから完全に解放される。
この「精神的な安心感」は、お金には代えられない、本当に大きなメリットだと私は思います。
フリマアプリとの比較!結局どっちがお得?
さて、ここまでフリマアプリと楽器買取サービスを比べてきましたが、一旦ここで整理してみましょう。
【フリマアプリ(メルカリ・ヤフオクなど)】
・メリット:もし、適正な価格設定ができて、良い購入者と出会え、完璧な梱包・発送ができれば、買取サービスよりも「高い金額」で売れる「可能性」がある。
・デメリット:梱包が地獄のように大変。送料・手数料が引かれて手取りが減る。配送破損や個人間トラブルのリスクが常にある。適正価格がわからないと売れない、または損をする。いつ売れるかわからない。
【楽器買取サービス】
・メリット:とにかく「楽」(梱包・発送の手間がほぼゼロ)。とにかく「早い」(出張買取なら即日現金化も)。とにかく「安心」(プロ査定で適正価格、個人間トラブル一切なし)。コストがかからない(送料・手数料無料)。
・デメリット:査定額は、フリマアプリで「完璧に取引できた場合の最高値」よりは、少し安くなるケースが多い。
こうして見比べると、一目瞭然ですよね。
たしかに、買取サービスは、業者がそれを買い取って、メンテナンスして、再度販売するための「利益」や「経費」を差し引いた金額を提示しますから、フリマアプリで個人に直接売る価格(いわば小売価格)よりは安くなるのが普通です。
でも、ちょっと思い出してください。
フリマアプリの販売価格から「手数料10%」と「高額な送料」と「梱包資材費」を引いた「手取り額」は、どうだったでしょうか?
もしかしたら、買取サービスの「査定額(=手取り額)」と、そんなに変わらないか、場合によっては逆転している…なんてことも、十分にあり得るんです。
「時間」「手間」「安心」という、目に見えないけれど非常に価値のあるものを犠牲にしてまで、フリマアプリで「わずかに高い手取り」を狙いにいくか。
それとも、それら全てを「プロに任せる」という安心感を選び、楽に、早く、確実に楽器を現金化するか。
どちらが自分にとって「賢い選択」か、もうお分かりいただけるのではないかと思います。
失敗しない「楽器買取サービス」の賢い選び方 5つのポイント

さて、前の章までのお話で、「なるほど、面倒な手間やリスクを考えたら、フリマアプリより楽器買取サービスを利用する方が、自分にとっては『賢い選択』かもしれないな」と感じていただけたかと思います。
でも、そう思って「楽器 買取」とインターネットで検索してみると…。
まあ、出てくるわ出てくるわ、本当にたくさんの買取サービスが見つかりますよね。
「どこも似たようなことが書いてあるけど、一体どの業者を選べばいいんだろう?」
こうして、次の「選択」に迷ってしまう方も少なくないと思うんです。
そうなんです、せっかく買取サービスを使うと決めても、その「サービス選び」に失敗してしまうと、結局「思ったよりずっと安い値段で買い叩かれた…」「手続きがやたら面倒だった…」「キャンセルしたら、返送料を請求されて損した…」なんていう、残念な結果にもなりかねません。
そこで、ここでは「失敗しない」ための、賢い「楽器買取サービス」の選び方として、あなたが事前にチェックすべき「5つの重要なポイント」を、中立的な視点でまとめてみました。
この基準で比較検討すれば、きっとあなたに合った、信頼できるサービスが見つかるはずですよ。
ポイント1:自分の楽器のジャンルに強いか(専門性)
まず最初にチェックしてほしいのが、その買取サービスが「あなたの売りたい楽器のジャンルに強いか?」、つまり「専門性」があるかどうかです。
「楽器買取」と一口に言っても、業者さんによって得意・不得意な分野があるんですよね。
例えば、フェンダーやギブソンといった王道のエレキギターやベースの扱いに非常に強いお店もあれば、サックスやトランペット、フルートといった「管楽器」を専門にしているお店もあります。
また、古いビンテージのアンプやエフェクターの価値に詳しいお店、シンセサイザーやDJ機材などの「デジタル楽器・電子楽器」に特化しているお店など、本当に様々です。
もし、あなたがすごく貴重なビンテージギターを売りたいのに、そういう知識が乏しく、主に入門用の楽器ばかりを扱っている業者に査定に出してしまったら…どうなるでしょう?
その楽器の本当の価値を見抜けず、相場よりもずっと安い査定額が提示されてしまう可能性が高いですよね。
これでは、フリマアプリで相場を知らずに売るのと、あまり変わらなくなってしまいます。
これを見極めるには、その業者のウェブサイトをしっかり見て、「買取実績」や「取扱商品」のページをチェックするのが一番です。
そこに、あなたが売りたい楽器と同じジャンルのものや、似たようなモデルが数多く掲載されていれば、「ああ、このお店はこの分野に詳しそうだな」と判断できますよね。
自分の大切な楽器の価値を正しく判断してもらうために、この「専門性」のチェックは欠かせないポイントだと私は思います。
ポイント2:買取方法が選べるか(出張・宅配・持込)
次のポイントは、「買取方法の選択肢」です。
前の章でも少し触れましたが、楽器の買取方法には、大きく分けて3つのパターンがあります。
1つ目は、業者のスタッフが自宅まで来てくれる「出張買取」。
2つ目は、楽器をダンボールに詰めて業者に送る「宅配買取」。
3つ目は、自分で楽器をお店まで持っていく「持込買取」です。
どの方法がベストかは、あなたの状況や売りたい楽器によって、まったく違ってきます。
例えば、売りたいものがギターやベース、電子ピアノなどで「大きくて重い」場合や、「アンプやエフェクターもまとめて、一度に10点以上売りたい」という場合は、どう考えても家まで来てもらう「出張買取」が圧倒的に楽ですよね。
何しろ、梱包の手間が一切かからないわけですから。
逆に、「売りたいのはエフェクター1個だけ」とか、「地方に住んでいて、近くに出張や持込ができるお店がない」という方なら、「宅配買取」が現実的な選択肢になります。
また、「家のすぐ近所にそのお店がある」「とにかく急いでいて、今すぐその場で現金にしてほしい!」というせっかちな方(私です)なら、「持込買取」が最速です。
優良なサービスというのは、こうした利用者の様々な事情やニーズに応えられるように、これら複数の買取方法をちゃんと用意してくれていることが多いです。
「うちは宅配買取しかやってません」とか「出張は関東だけです」といった制限がないか、自分の希望する買取方法が利用できるかを、事前に確認しておきましょう。
ポイント3:査定料や送料、キャンセル料などの手数料は?
さて、これはお金に直結する、非常に重要なチェックポイントです。
「買取サービスは、フリマアプリと違って手数料がかからないのがメリット」とお話ししましたが、それはあくまで「優良な」サービスに限った話なんです。
世の中には、残念ながら色々な名目で手数料を引こうとする業者も存在するかもしれません。
ですから、そのサービスのウェブサイトを見て、以下の項目が「すべて無料」とはっきり書かれているかを、あなたの目で必ず確認してください。
・「査定料」や「見積料」
・「(宅配買取の場合の)送料、梱包キット代」
・「(出張買取の場合の)出張料」
・「(買取が成立した際の)銀行振込手数料」
正直、今どきのまともな楽器買取サービスなら、これらが無料なのは「当たり前」と言ってもいいくらいです。
本当に注意すべきは、その次です。
それは、「査定額に納得いかなかった場合のキャンセル料」と、特に「宅配買取で送った後の『返送料』」です。
考えてみてください。
宅配買取で楽器を送ったら、「査定額は5,000円です」と連絡が来たとします。
あなたが「えー、安すぎる!それなら売るのやめます。返してください」と言った時、もし業者から「わかりました。
では、返送しますが、その時の送料2,500円はお客様のご負担(着払い)となります」と言われたら、どうしますか?
5,000円で渋々売るか、2,500円払って返してもらうか…という、最悪の二択を迫られることになりますよね。
これでは、安心して査定に出すことなんてできません。
だからこそ、「査定額にご納得いただけなかった場合の、キャンセル料や返送料も、すべて当店が負担します(=無料です)」と、はっきりとウェブサイトに明記しているサービスを選ぶことを、私は強く、強く、おすすめします。
これは、業者が自分たちの査定額に自信を持っている証拠でもある、と私は感じています。
ポイント4:査定額の承認から入金までのスピード
4つ目のポイントは、「スピード感」です。
使わない楽器を売るからには、「できるだけ早くお金に換えたい」というのが、正直な気持ちですよね。
この「査定」から「入金」までのスピードも、買取方法や業者によって、かなり差が出てくるところです。
先ほども少し触れましたが、最もスピーディーなのは、やはり「持込買取」です。
お店に楽器を持っていき、その場で査定してもらい、金額に納得すれば、その場で現金で受け取れる(あるいは即日振込)というのが基本の流れです。
「出張買取」もかなり早いです。
自宅で査定してもらい、OKならその場で現金払い、というケースも多いようです(高額な場合は、安全のために翌営業日などに銀行振込、という対応になることもあります)。
一方で、最も時間がかかるのが「宅配買取」です。
これは、仕組み上どうしても仕方ないんですよね。
まず、あなたが(1)無料の梱包キットを取り寄せ、(2)楽器を梱包して発送し、(3)それが業者の倉庫に到着します。
そこから(4)査定スタッフが順番に中身を確認して査定結果を出すまでに、だいたい1〜3営業日くらい。
(5)その結果がメールなどであなたに知らされ、あなたが「その金額でOKです」と返信(承認)し、ようやく(6)振込手続きが開始され、あなたの口座に入金される(1〜2営業日後)…という流れです。
トータルで見ると、申し込みから入金まで、1週間から、長いと10日くらいかかることも想定しておいた方が良いでしょう。
別に急いでないよ、という方なら問題ありませんが、もし「今月中に現金が必要!」といった事情がある方は、このタイムラインは重要ですよね。
優良なサービスは、「商品到着後、〇営業日以内に査定結果をご連絡」「ご承認いただき次第、〇営業日以内にお振り込み」といった「目安の時間」を、ウェブサイトにきちんと明記しているものです。
このスピード感も、あなたのニーズと合っているかを確認してみてください。
ポイント5:口コミや評判、運営実績の信頼性
さて、最後の5つ目のポイントです。
色々とお話ししてきましたが、結局のところ、これが一番大事かもしれないと私は思っています。
それは、その買取サービス(を運営している会社)が、「信頼できるか」どうかです。
何しろ、人によっては何十万円もするかもしれない、あなたの大切な楽器を預けるわけです。
査定額がどうとか、スピードがどうとかいう以前に、怪しい業者や、対応が雑な業者には、絶対に頼みたくないですよね。
では、どうやって「信頼性」を見極めるか?
一つは、やはりインターネット上の「口コミ」や「評判」をリサーチすることです。
Googleマップにそのお店のレビューが投稿されていないか、X(旧Twitter)などでそのサービス名(会社名)を検索してみると、実際に利用した人の「生の声」が見つかることがあります。
「査定額が思ったより高かった」「スタッフの電話対応が丁寧だった」というポジティブな声もあれば、「査定結果の連絡が遅すぎる」「思ったより安かった」といったネガティブな声もあるでしょう。
(あまりにも「絶賛」の口コミばかりがキレイに並んでいるのも、逆にちょっと不自然な感じがしますけどね…)
ある程度の賛否両論がある中で、全体として誠実そうな運営をしているか、というのが一つの判断材料になります。
そして、もう一つが「運営実績」の確認です。
そのサービスのウェブサイトにある「会社概要」や「運営者情報」のページを必ず見てください。
そこに、運営している会社名、住所、電話番号などがきちんと書かれているか。
どのくらいの期間、そのサービスを続けているのか(運営歴が長いほど、一つの信頼にはなりますよね)。
そして何より、警察(公安委員会)から許可を得た証である「古物商許可番号(第〇〇〇〇号)」が、ちゃんと記載されているかを確認しましょう。
中古品を売買するビジネスは、法律でこの「古物商許可」の取得と、番号をウェブサイト等に明記することが義務付けられています。
もし、サイトのどこを探してもこの番号が見当たらないような業者がいたら、その時点で「論外」です。
こうした客観的な情報(許可番号や運営実績)と、主観的な情報(口コミ)を総合的に見て、「ここなら、私の大切な楽器を安心して任せられそうだな」と、あなたが直感的に思えるサービスを選ぶこと。
それが、失敗しないための一番の近道だと、私は思います。
参考までに:どんなサービスがある?有名な楽器買取サービス例

さて、前の章では「失敗しない楽器買取サービスの賢い選び方」として、5つの重要なチェックポイントをご紹介しました。
「専門性」「買取方法」「手数料」「スピード」「信頼性」…。
こうした基準はわかったけれど、「そうは言っても、具体的にどんなサービスがあるのか、今ひとつイメージが湧かない…」と感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
たしかに、いきなり自分でゼロから探すのは大変だと思います。
そこで、ここでは「あくまで参考として」、日本で広く知られていて、多くの方が利用した経験があるであろう「有名(大手)」な楽器買取サービスをいくつかピックアップし、それぞれの「特徴」を簡単にご紹介してみたいと思います。
(※これは「おすすめランキング」や「優劣」を決めるものでは、決してありません。
あなたがご自身で比較検討する際の「たたき台」として、参考にしてみてくださいね。)
ここで紹介するような大手サービスは、前の章で挙げた「5つのポイント」のうち、基本的な部分(査定料・送料・振込手数料無料、古物商許可の明記など)は、ほとんどクリアしていることが多いです。
ただし、キャンペーンや規約の変更は常にあることなので、もし気になったサービスがあれば、最終的には必ずご自身で公式サイトの最新情報をチェックするようにしてくださいね。
大手総合楽器店ならではの安心感「イシバシ楽器」
まず最初にご紹介するのは、「イシバシ楽器」の楽器買取サービスです。
「イシバシ楽器」といえば、もう日本を代表する老舗の大手総合楽器店の一つですよね。
楽器を演奏する方なら、一度はお店の名前を聞いたことがあるか、実際に利用したことがあるのではないでしょうか。
こうした「大手楽器店」が運営している買取サービスの最大の魅力は、やはり長年の販売・買取実績に裏打ちされた「楽器に対する専門性の高さ」と、その知名度から来る「圧倒的な安心感」だと私は思います。
特に、フェンダーやギブソンといった王道のギター・ベース類、人気の高いエフェクターなどの分野では非常に強く、専門知識豊富なスタッフがしっかり査定してくれるという信頼感がありますよね。
また、古いビンテージ楽器や中古市場での価値が分かりにくい機材についても、その価値を正しく見抜いてくれる可能性が高いと感じます。
買取方法は「店頭持込」「宅配買取」「出張買取」の3種類に、しっかり対応してくれています。
全国に展開している実店舗に直接持ち込むこともできますし、忙しい方や近くにお店がない方のために、無料の梱包キット(ダンボールや緩衝材)を送ってくれる「宅配買取」も非常に便利です。
大型楽器や点数が多い場合は、「出張買取」(※対応エリアは要確認)も選べます。
もう一つの大きな特徴として、「下取(したどり)」に力を入れている点が挙げられます。
これは、今持っている楽器を売るだけでなく、「イシバシ楽器で新しい楽器を買う(買い替える)」ことを条件に、通常の買取査定額よりも高く買い取ってくれるサービスです。
もし、あなたが「この楽器を売ったお金で、次はあのギターが欲しいな」と漠然とでも考えているなら、この「下取」はものすごく大きなメリットになりますよね。
「長年の実績がある大手じゃないと不安」「専門的な目でしっかり見てほしい」「買い替えも検討している」という方にとっては、非常に有力な選択肢の一つになると思います。
全国展開とアクセスの良さ「島村楽器」
次にご紹介するのも、イシバシ楽器と並ぶ、もう一つの超大手総合楽器店「島村楽器」の買取サービスです。
「島村楽器」も、知らない人はいない、というくらい有名な楽器店チェーンですよね。
このサービスの最大の強みは、なんといってもその「店舗数の多さ」と「アクセスの良さ」ではないでしょうか。
北は北海道から南は沖縄まで、全国の主要都市はもちろん、郊外の大型ショッピングモールやイオンモールの中など、「え、こんなところにも?」と思うくらい、私たちの身近な場所に実店舗があります。
この「店舗網」が、楽器買取において大きなメリットになるんです。
つまり、「店頭持込買取」のハードルが、他のどこよりも低いんですよね。
「仕事帰りや、週末に家族と買い物に来たついでに、ちょっと楽器の査定をお願いしようかな」ということが、気軽にできてしまいます。
もちろん、島村楽器も「宅配買取」(無料梱包キットあり)や「出張買取」といった、他の買取方法にもしっかり対応しています。
取り扱っている楽器のジャンルも、さすがは総合楽器店。
ギター、ベース、アンプ、エフェクターはもちろん、管楽器(サックス、トランペット、フルートなど)、電子ピアノ、キーボード、シンセサイザー、ドラム類、DJ機材まで、本当にオールマイティに対応してくれる安心感があります。
そして、こちらもイシバシ楽器と同様に、「下取」サービスに非常に力を入れています。
島村楽器で新しい楽器を購入するなら、買取査定額が通常よりもアップ(※条件は要確認)するというものです。
「家の近く、あるいはよく行くショッピングモールに島村楽器がある」「売りたい楽器がギター以外(管楽器や電子ピアノなど)だ」「新しい楽器への買い替えも、ちょっと考えている」という方には、とても便利で心強いサービスだと感じます。
ネット特化型の手軽さとスピード感「楽器高く売れるドットコム」
最後にご紹介するのは、前の2つとは少しタイプの違うサービスです。
「楽器高く売れるドットコム」は、実店舗の楽器販売をメインにしているというよりは、「インターネットでの買取(リユース)」に特化して大きく成長してきたサービスですね。
(「高く売れるドットコム」という名前は、楽器以外(家電やカメラなど)の買取でも耳にしたことがある方が多いかもしれません。)
運営しているのは「株式会社マーケットエンタープライズ」という、東証プライム市場に上場している大きな会社です。
上場企業が運営しているということで、その点での「信頼性」や「個人情報の取り扱い」などに関する安心感は非常に高いと言えるでしょう。
このサービスの特徴は、インターネットに特化しているからこその「手軽さ」や「スピード感」を追求している点にあると私は感じています。
買取方法は「宅配買取」「出張買取」「持込買取(全国にあるリユースセンターへの持込)」の3つに対応。
特にユニークなのが、ウェブや電話での「事前査定」に力を入れている点です。
これは、売りたい楽器のメーカー名、型番、状態(キズの有無など)を伝えるだけで、「現時点での買取上限額(目安)は、およそ〇〇円です」と、楽器を送る「前」に教えてくれるサービスなんです。
もちろん、最終的な金額は実物を見てから決まりますが、目安が先にわかるのは、すごく安心ですよね。
フリマアプリのデメリットで挙げた「適正価格がわからない」という不安や、宅配買取でありがちな「送ってみたけど、提示された額が安すぎてガッカリ…」というミスマッチを、かなり減らすことができる工夫だと思います。
取り扱いジャンルも、楽器全般(ギター、ベース、アンプ、エフェクター、管楽器、弦楽器、DJ機材、ドラムなど)幅広く対応しています。
「楽器店に持っていくのはちょっと面倒だな」「まずは、送る前に手軽に査定額の目安だけでも知りたい」という、現代のインターネットユーザーのニーズに、うまく応えているサービスの一つだと言えそうですね。
まとめ
ここでは、使わなくなった楽器を売る方法として、「メルカリ・ヤフオクなどのフリマアプリ」と「楽器買取サービス」を詳しく比較してきました。
フリマアプリには「自分で価格を決められる(高く売れる可能性)」という魅力がある一方で、「梱包・送料・手数料」といったコストと手間、さらには「個人間トラブル」や「そもそも売れない」という、致命的とも言える多くのデメリットが潜んでいましたね。
それらの問題をすべて回避できる「賢い選択肢」が、専門の「楽器買取サービス」です。
フリマアプリの最高値よりは安くなるかもしれませんが、「楽さ」「早さ」「安心感」を手間なく得られるのは、何物にも代えがたいメリットだと私は思います。
あなたが何を一番優先したいのかを考え、この記事で紹介した「5つの選び方」も参考にして、あなたの大切な楽器にとってベストな方法を選んでみてくださいね。
関連記事のご紹介
ここでは、メルカリやヤフオクといった「フリマアプリ」と「楽器買取サービス」の比較に焦点を当てて、詳しく掘り下げてきました。
でも、いざ「楽器を手放そう」と決めた時には、他にも色々な疑問や悩みが出てくるものですよね。
例えば、「買取業者やフリマアプリ以外も全部ひっくるめて、結局どこが一番いいの?」とか、「専門業者じゃなくて、近所のリサイクルショップに持ち込むのはどうなんだろう?」、あるいは「もう壊れてて音も出ないんだけど、これって売れるのかな…?」といった、様々なケースが考えられると思います。
そうした、さらに詳しい情報や、あなたの楽器の状況に合わせた最適な売り方について、他にも記事をいくつか用意しています。
もしよければ、あなたの今の悩みに一番近いものを、ぜひチェックしてみてくださいね。
- フリマアプリや買取業者だけでなく、オークションなども含めた全ての売却手段を、公平な視点でメリット・デメリットを比較して、自分に最適な方法をじっくり選びたい方は、まずこちらの記事を読んでみると全体像が掴めると思います。楽器を売るならどこがいい?買取業者・フリマアプリ・オークション徹底比較
- 「専門の楽器店に持っていくのはちょっと敷居が高いな…」「手っ取り早く、家の近くにある総合リサイクルショップに持ち込んじゃうのはアリ?」と迷っている方へ。専門の買取店と何が違って、どんなメリットやデメリットがあるのかを、こちらで詳しく解説しています。地元のリサイクルショップに楽器を持ち込むのはアリ?専門買取との違い
- 「もう音が出ない」「ネックが折れて(反って)しまった」「パーツが足りない」…。そんな故障・破損した楽器を前に、「これはもう粗大ゴミかな…」と諦めかけていませんか?いえいえ、そんなジャンク品でも売れる可能性はあります!修理に出すべきか、そのまま売るべきかの判断基準をまとめました。壊れた楽器・ジャンク品でも売れる?修理して売るべきか
- あなたが手放そうとしている楽器が、ただ古いだけではなく、「貴重なヴィンテージ楽器」や「ギブソン、フェンダーなどのハイブランド楽器」である場合、絶対にその価値がわからないお店に売ってはいけません。その貴重な価値を正しく評価してもらい、一番「高く」売るための最善の方法を、こちらでご紹介しています。ヴィンテージ楽器・ハイブランド楽器を「高く」売るための一番良い方法