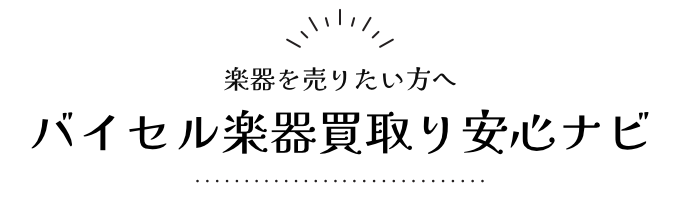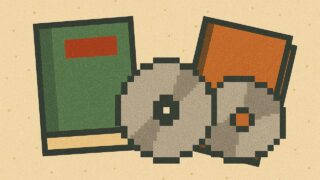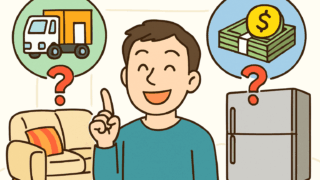学生時代に夢中になって練習したギター。
バンドを組んで、汗と涙を流したベース。
あるいは、衝動買いしてしまったエフェクターやシンセサイザー…。
最近すっかり弾く機会が減って、部屋の隅や押入れの中で、ホコリをかぶってしまっていませんか?
「よし、大切にしてくれる次の人に譲ろう!」と、売ることを決意したのは良いものの、ここで次の大きな悩みにぶつかりますよね。
「一体、どこで売るのが一番“賢い”んだろう?」って。
「フリマアプリ(メルカリとか)で売れば、高く売れるかもしれないなぁ…」
「でも、ギターの梱包とか発送作業のことを想像すると、正直めちゃくちゃ気が重い…」
「かといって、よく分からないリサイクルショップに持っていって、二束三文で買い叩かれたら、それはそれで悔しいし…」
「高く売りたい気持ち」と、「面倒くさい気持ち」。
この2つが頭の中で戦って、結局「また今度でいっか」と、先延ばしにしてしまっている…なんてこと、ありませんか?
その悩み、すごくよく分かります。
実は、楽器の売り方の「正解」って、あなたが「何を一番重視するか」によって、人それぞれ全然違うんです。
ここでは、今どきの主な楽器の売り方を、「価格(手残り)」「手間(楽さ)」「スピード」「安心感(トラブルリスク)」といった、あなたが気になるであろう全ての視点から、徹底的に比較検討していきます。
それぞれのメリットと、そしてもちろん「デメリット」も包み隠さず丸裸にしますね。
楽器を売る前に知っておきたい!3つの主な方法と特徴

大切にしてきた楽器を手放そうと決めた時、まず「これ、どこで売るのが一番いいんだろう?」って悩みますよね。
僕も昔、使わなくなったギターを売ろうとした時、とりあえず近所の楽器屋さんに持っていった経験があります。
でも、今は本当に選択肢が増えました。
大きく分けると、主な方法は3つあると思うんです。
ひとつは昔ながらの「楽器買取業者」。
そして今どきの「フリマアプリ」。
最後に、根強い人気のある「ネットオークション」。
ここでは、本格的な比較に入る前の準備運動として、この3つの方法がそれぞれどんな特徴を持っているのか、まずはざっくりと全体像を掴んでいきましょう。
「あ、自分にはこの方法が合ってるかも」なんてイメージしながら読んでもらえると嬉しいです。
それぞれのメリット、そして「ちょっと面倒な点」も紹介していきますね。
1. 専門知識で安心「楽器買取業者(店舗・宅配・出張)」
まずは「楽器買取業者」です。
これは、文字通り楽器の買取を専門にしているプロ集団、というイメージですね。
リサイクルショップなども含まれますが、ここでは特に「楽器専門店」をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
この方法の最大のメリットは、なんといっても「専門知識を持ったスタッフが査定してくれる安心感」だと思います。
ギターやベース、エフェクター、管楽器など、その楽器のブランド価値や、状態、今の市場での相場なんかをしっかり理解した上で値段をつけてくれる。
これが素人相手の取引だと「この価値、分かってもらえてるかな?」って不安になりますもんね。
それに、最近の買取業者はサービスがすごく充実してるんですよ。
昔みたいに「お店に持っていく(店舗持込)」だけじゃなくて、「ダンボールに詰めて送るだけ(宅配買取)」や、「家まで査定に来てもらう(出張買取)」が選べるのが当たり前になってきました。
特に、アンプや電子ピアノみたいな大きくて重い楽器、あるいは楽器の数がたくさんある場合、家から一歩も出ずに売れる出張買取や宅配買取は、めちゃくちゃ便利です。
「とにかく面倒な手続きはイヤ」「早く確実に売りたい」という人には、一番向いている方法だと感じますね。
ただ、その分、フリマアプリなんかで自分で売るよりは、買取価格が少し控えめになる傾向がある、という点も知っておくと良いと思います。
2. 手軽さで人気「フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)」
次に、ここ数年ですっかりお馴染みになった「フリマアプリ」です。
メルカリやラクマなんかが有名ですよね。
この方法の魅力は、ずばり「手軽さ」と「価格設定の自由度」かなと思います。
スマホで売りたい楽器の写真を撮って、説明文を書いて、値段を決めて出品。
本当にこれだけで、全国の「欲しい人」に向けて販売が開始できちゃうわけです。
自分で値段を決められるので、例えば業者の査定が1万円だったものでも、フリマアプリで1万5千円で売れる、なんてことも全然あり得ます。
利用者もすごく多いので、状態の良い人気モデルなんかは、出品して数分で売れちゃった!なんて話もよく聞きますよね。
しかーし、この「手軽さ」の裏には、結構な「手間」が隠れているのも事実なんです。
メタキーワードにも「メルカリ デメリット」とあるように、ここが気になる点ですね。
例えば、「もう少し安くなりませんか?」っていう値下げ交渉のコメント対応。
そして、売れた後に待っている「梱包」と「発送」の作業。
特に楽器の梱包って、思った以上に大変なんですよ。
ギター一本送るにも、まず適切なサイズのダンボールを探して、楽器が壊れないように厳重にプチプチ(緩衝材)を巻いて…。
これを「手軽」と呼んでいいのか、ちょっと悩ましいところです。
3. 思わぬ高値も?「ネットオークション(ヤフオクなど)」
3つ目は、「ネットオークション」です。
ヤフオク(Yahoo!オークション)なんかが代表的ですね。
フリマアプリが「決まった値段」で売るのに対して、オークションは「欲しい人が値段を競り合う」のが最大の特徴です。
ここにロマンがあるというか(笑)。
もし、あなたが売ろうとしている楽器が、すでに生産終了しているビンテージ品だったり、すごく希少な限定モデルだったりした場合。
そういう「探しているマニア」がいる楽器は、オークションに出すと価格がどんどん上がっていく可能性があります。
業者の査定額やフリマでの相場を、大きく超える「思わぬ高値」がつくことも夢じゃないんですね。
それに、オークションには「最低落札価格」っていうのを設定できる機能もあります。
「これ以下の値段では売りたくないな」というラインを決めておけるので、変に安く買い叩かれてガッカリする、という事態を防げる安心感もあります。
ただし、デメリットもあって。
フリマアプリと同じように、出品作業や、落札後の梱包・発送の手間はガッツリかかります。
むしろ、フリマよりマニアックな人が見ている印象もあって、より専門的な質問が飛んでくることもありますね。
あと、オークションは通常1週間とか期間を決めて開催するので、落札されて、入金を確認して、発送して…と、現金を手にするまでのスピードは遅めになりがちです。
4. どの方法が自分に合ってる?目的別の早分かりチャート
さて、ここまで3つの方法の特徴をざっと見てきました。
「どれも一長一短あって、余計に迷ってきたかも…」と思ったかもしれませんね。
ここで一度、あなたが「楽器を売る上で何を一番重視したいか」を基準に、3つの方法を整理してみましょう。
簡単な比較表(チャート)を作ってみました。
(◎:とても良い ○:良い △:イマイチ)
| 比較ポイント | 楽器買取業者 | フリマアプリ | ネットオークション |
|---|---|---|---|
| 買取価格の高さ(期待値) | △ | ○ | ◎ |
| 手間(楽さ) | ◎ | △ | △ |
| 現金化のスピード | ◎ | ○ | △ |
| 安心感(トラブルリスク) | ◎ | △ | △ |
どうでしょうか。
こうして見ると、特徴がハッキリ分かれますよね。
例えば、「価格はそこそこでもいいから、とにかく楽に、早く、安心して売りたい」なら「楽器買取業者」が圧倒的に良さそうです。
逆に、「手間がかかってもいいから、1円でも高く売りたい。あわよくば高騰狙い!」なら「オークション」や「フリマアプリ」が候補になります。
ご自身の優先順位をちょっと考えてみると、どの方法を軸に検討すべきか、ぼんやりと見えてくるんじゃないかなと思います。
5. まずは自分の楽器の「売りやすさ」をチェックしよう
どの方法で売るか、という視点と同時にもう一つ。
すごく大事なのが、「じゃあ、自分が売ろうとしている楽器って、どういうモノだっけ?」を客観的にチェックすることです。
というのも、すべての楽器が、すべての方法でスムーズに売れるとは限らないからなんですね。
例えば、フェンダーやギブソン、ヤマハといった「有名ブランド」の「人気モデル」で、状態もかなり良いもの。
こういう楽器なら、フリマアプリでも「欲しい!」という人がたくさんいるので、すぐに売れる可能性が高いです。
でも、もし売るのが「電子ピアノ」や「ドラムセット」だったらどうでしょう?
これをフリマやオークションで売るとなると、まず「どうやって発送するの?」という巨大な壁にぶつかります。
送料だけで数万円かかったり、そもそも運送会社が受け付けてくれなかったり。
こういう大型楽器は、家まで引き取りに来てくれる「出張買取」が、ほぼ唯一の現実的な選択肢になったりします。
あるいは、音が鳴らない、ネックが反っているなどの「故障品(ジャンク品)」や、ちょっとマニアックな「マイナーブランド」の楽器。
こういうのは、フリマで売ろうとしてもなかなか買い手がつかなかったり、価値を分かってもらえなかったりします。
でも、専門の買取業者なら「修理して再販できる」とか「パーツとしての価値がある」と判断して、値段をつけてくれるケースもあるんです。
まずはご自身の楽器の「ブランド」「状態」「サイズ(重さ)」を冷静に見てみて、「この楽器、どの方法なら一番スムーズに売れそうかな?」と考えてみるのが、後悔しないための第一歩だと思いますよ。
【徹底比較】楽器買取業者 vs フリマアプリ vs オークション

さて、第1章では3つの売り方の「ざっくりとした特徴」を見てきました。
ここからが本番です。
この章では、「結局、自分にとってはどれが一番お得で、一番楽なの?」という、みなさんが一番知りたい核心部分について、5つの具体的なポイントで徹底的に比較検討していきます。
「なんとなく業者が楽そう」とか「フリマが高く売れそう」といったイメージを、もっとハッキリとした「確信」に変えていきましょう。
比較するポイントは、次の5つです。
1. 買取価格(手残り)の高さ
2. 手間と時間(出品・梱包・発送)
3. 現金化までのスピード
4. 専門知識の必要性
5. トラブル(クレーム・返品)のリスク
この5つを比べれば、あなたにとっての「最適解」がきっと見つかると思いますよ。
それでは、ひとつずつじっくり見ていきましょう。
比較ポイント1:買取価格(手残り)の高さ
まず、やっぱり一番気になるのは「お金」の話ですよね。
「どこが一番高く売れるの?」という点。
あくまで一般的な傾向として、純粋な「売れる価格」のポテンシャル(期待値)だけ見れば、こんな順番になることが多いです。
ネットオークション > フリマアプリ > 楽器買取業者
オークションは、希少なビンテージ品なんかに熱狂的なファンが競い合うと、とんでもない値段がつくことがありますからね。
フリマアプリも、業者の買取相場よりは高い値段で売れることがほとんどです。
「じゃあ、やっぱりフリマかオークションじゃん!」と思うかもしれません。
しかーし、ここでめちゃくちゃ大事なのが、「売れた価格(額面)」と、最終的に自分の銀行口座に入金される「手残り」は違う、ということなんです。
フリマアプリやオークションの場合、まず「売れた価格」から「販売手数料」が引かれますよね。
メルカリなら10%とか、結構大きい割合です。
さらに、そこから「送料」が引かれます。
楽器の送料って、みなさんが思っているより高いんですよ。
ギター1本送るにも、サイズが大きいですから安くても2,000円前後、アンプや電子ピアノなんてことになれば、数千円から1万円以上かかることもあります。
一方、楽器買取業者の場合、多くが「送料・手数料・査定料すべて無料」をうたっています。
つまり、「査定額 = ほぼそのまま手残り」になるケースが多いんです。
例えば、業者の査定額が20,000円だったギター。
これをフリマアプリで25,000円で売ったとします。
ここから手数料10%(2,500円)と、送料(仮に2,000円)を引くと、手残りは 20,500円。
どうでしょう?
もちろんフリマの方が少し高いですが、その差はたった500円。
もしこれがもっと重いアンプで、送料が5,000円かかったとしたら、手残りは 17,500円になって、業者に売った方が高かった、なんていう「逆転現象」も普通に起こるわけです。
「額面」に惑わされず、「手残り」で比べることが本当に大事ですね。
比較ポイント2:手間と時間(出品・梱包・発送)
次に比較したいのが「手間」です。
人によっては、「価格差がちょっとくらいなら、面倒なのは絶対にイヤ」という人も多いんじゃないでしょうか。
この「手間(楽さ)」という観点で見たら、もうこれは圧倒的です。
楽器買取業者 >>>> フリマアプリ = ネットオークション
もう、比べ物にならないくらい、「楽器買取業者」が楽ちんですね。
特に「宅配買取」や「出張買取」を選んだ場合、私たちがやることは、せいぜいWebで申し込んで、身分証のコピーを用意するくらい。
宅配買取なら、業者が送ってくれたダンボールに楽器を詰めて(この梱包材すら無料のところも多いです)、集荷に来てもらうだけ。
出張買取なら、約束の日時に査定員さんが家に来て、楽器を見て、値段が決まればその場で持って行ってくれます。
なんなら、こっちは座って見ているだけです。
一方で、フリマアプリやオークションは、正直「手間の塊」と言ってもいいかもしれません。
まず、出品するために「写真撮影」。
キレイに撮るのはもちろん、キズや汚れの部分も後でトラブルにならないように、あえてしっかり撮る必要があります。
次に「商品説明文の作成」。
型番や状態、音出し確認の結果などを詳しく書かないといけません。
出品したらしたで、「〇〇さん、はじめまして。購入を検討しているのですが、1,000円お値引き可能でしょうか?」みたいなコメント対応や、マニアックな質問に答える必要も出てきます。
そして、売れた後に待っている最大の難関が、「梱包」と「発送」です。
ギターがぴったり入るダンボール、どこで手に入れますか?
楽器を衝撃から守るための大量のプチプチ(緩衝材)、買わないといけません。
ネックが動かないように固定して、厳重に梱包して…この作業だけで、慣れていないと1時間以上かかることも普通です。
梱包が終わったら、それをコンビニや運送会社の営業所に持っていくか、集荷を依頼する。
この一連の手間と時間を、自分の時給に換算してみてください。
「あ、買取業者に出す方がトータルで得かも」と感じる人も、結構多いと思いますよ。
比較ポイント3:現金化までのスピード
3つ目は「スピード感」。
「引っ越しが迫ってるから、今週末までに処分したい!」とか「急な出費で、とにかく早く現金が欲しい!」という場面、ありますよね。
この「現金化までのスピード」で比較すると、これも「楽器買取業者」の圧勝です。
楽器買取業者 > フリマアプリ > ネットオークション
「店舗買取」が一番早いです。
お店に楽器を持っていけば、その場で査定してくれて、金額に納得すれば、その場で現金を受け取って終了。
数時間、いや早ければ30分程度で完結します。
「宅配買取」や「出張買取」の場合でも、スピード感はかなりのもの。
楽器が業者に到着(または査定員が訪問)して、査定結果の連絡が来て、それに「OKです」と返事をすれば、早ければ当日、遅くとも翌営業日とかには指定口座に振り込んでくれる業者がほとんどです。
じゃあ、フリマアプリはどうでしょう。
これは「売れるまでの時間」がまったく読めません。
人気ブランドの人気モデルなら、出品した瞬間に売れることもあります。
でも、ちょっとマイナーな楽器や、値段を高めに設定しすぎると、1ヶ月経っても、3ヶ月経っても「いいね!」がつくだけで売れない…なんてこともザラにあります。
売れた後も、「発送して→購入者が受け取って→購入者が中身を確認して「評価」をして→ようやく売上が計上されて→そこから自分で「振込申請」をして→数日後に入金される」という長い道のりがあります。
オークションは、もっとも時間がかかりますね。
まず、出品期間として「7日間」とか設定するのが一般的です。
高値がつくのを待つ時間が必要ですからね。
オークションが終了して、落札者が決まって、そこから落札者が支払い手続きをして、入金が確認できてから発送して…と、現金を手にするまでには、早くても1週間〜10日は見ておいた方がいいでしょう。
「スピード」が最優先なら、買取業者一択、と言っていいと思います。
比較ポイント4:専門知識の必要性
これ、意外と見落としがちなポイントなんですけど、「楽器を売る側(つまり自分)」に、どのくらい専門知識が必要か?という問題です。
これも、結論から言うとこうなります。
フリマアプリ・オークション:知識が「必要」
楽器買取業者:知識は「不要」
もし、あなたが売ろうとしている楽器について、型番も、いつ頃のモデルかも、今の状態(ネックが反ってないか、フレットは何割残ってるか、電装系にガリはないか)も、ぜんぶ完璧に説明できるなら、フリマやオークションでも大丈夫です。
でも、もし「親戚から譲り受けたもので、よく分からない」とか「ギター弾くけど、細かいメンテナンスのことはちょっと…」という場合。
この場合は、「楽器買取業者」に任せるのが絶対に安全です。
なぜなら、買い手である業者が「プロ」だから。
こっちが何も言わなくても、「あ、これは〇〇年のモデルですね」「ここが少し白濁してますが、音は良いですね」と、全部向こうが判断して、その価値に見合った適正な価格をつけてくれます。
知識がないことで、不当に買い叩かれる心配がないんです。
逆に、フリマアプリやオークションは、売る側が「プロ」として振る舞う必要があります。
まず「値段設定」。
今の相場を知らないと、本当は5万円の価値があるものを「1万円」で出品して大損したり、逆に1万円の価値しかないものを「3万円」で出して、いつまで経っても売れない、なんてことになります。
そして「商品説明」。
「ネックの反りはありません(と自分では思ってる)」と書いて売ったのに、買った人から「めちゃくちゃ反ってるじゃないですか!」とクレームが来たら、どうしますか?
「自分は素人なので分かりませんでした」は、残念ながら通用しないことが多いんです。
自分の知識に自信がない楽器を売る時は、プロに査定してもらうのが一番賢明な判断だと思いますね。
比較ポイント5:トラブル(クレーム・返品)のリスク
最後の比較ポイント、これが精神的に一番キツいかもしれない「トラブルのリスク」です。
メタキーワードにあった「楽器 メルカリ デメリット」の、まさに核心部分がここかなと思います。
フリマアプリもオークションも、基本的には「個人」対「個人」の取引(CtoC)ですよね。
ここに、どうしてもリスクが潜んでいるんです。
まず、「楽器買取業者」との取引(これは「個人」対「企業」のBtoC)の場合。
トラブルリスクは、ほぼ「ゼロ」です。
査定額が提示されて、あなたが「その金額で売ります」と合意した瞬間、契約成立。
業者が楽器を引き取った後で、「やっぱりここにキズがあったから減額します」とか「やっぱり壊れてたから返品します」なんてことは、まずあり得ません(※もちろん、申告と著しく異なる場合などは別ですが)。
売ってしまえば、もうスッキリ終わり。安心感が違います。
さて、問題はフリマアプリやオークションです。
こちらは、常にトラブルの可能性があります。
一番多いのが、「説明と状態が違う」というクレーム。
「写真に写ってないキズがあった」
「アンプに繋いだらガリ(ノイズ)が出た。説明になかった」
「ネックが反っていて弾きにくい」
こういう連絡が購入者から来ると、本当に気が滅入ります。
「いや、送る前は大丈夫だった」と言っても、「届いた時点でこうなってる」と言われたら、水掛け論です。
もう一つの大きなリスクが、「輸送中の破損」。
これは、あなたがどれだけ完璧に梱包したつもりでも、ゼロにはできません。
運送会社が手荒に扱えば、ギターのネックなんて簡単に折れてしまいます。
その時、「出品者の梱包が不十分だった」のか「運送会社の過失」なのか、責任の所在をはっきりさせるのは非常に困難です。
結果として、返品・返金対応になったり、売上金が宙に浮いてしまったり…。
こういう面倒なやり取りや、精神的なストレスを一切感じたくない、という人は、個人間取引は避けた方が無難かもしれません。
買取業者の査定額がフリマより少し安いのは、この「トラブルリスク」を全部引き受けてくれる「安心料」込み、と考えることもできると思いますよ。
一覧比較表:あなたに最適な方法はどれ?
いやー、長々と5つのポイントで比較してきましたね。
頭がゴチャゴチャしてきたかもしれないので、最後にここまでの話を全部まとめた「比較一覧表」をドンと載せておきます!
(◎:最高 ○:良いp △:普通・やや難あり ×:悪い・高リスク)
| 比較ポイント | 楽器買取業者 | フリマアプリ | ネットオークション |
|---|---|---|---|
| 手残り期待値(※) | △ | ○ | ◎ |
| 手間(楽さ) | ◎ | × | × |
| 現金化スピード | ◎ | △ | × |
| 専門知識の要否(売る側) | ◎ (不要) | × (必要) | × (必要) |
| トラブルリスク | ◎ (低い) | × (高い) | × (高い) |
(※ 手残り期待値は、大型楽器などで送料が非常に高くなる場合、フリマ・オークションが業者を下回る「逆転現象」もあります)
どうでしょうか。
こうして見ると、本当に一長一短ですよね。
結局、「どの方法が一番!」と断言することはできなくて、「あなたが何を一番大切にするか」で答えが変わってくるんだと思います。
「梱包とか大好きだし、マメな性格。リスクも理解した上で、1円でも高く売りたい」という人なら、フリマアプリやオークションに挑戦する価値は十分にあります。
「楽器の知識ゼロ。とにかく忙しいから、今すぐストレスなく、安全に現金化したい」という人なら、楽器買取業者を選ぶのが賢明な判断です。
ご自身の性格や、楽器の状態、置かれている状況を考えながら、ベストな方法を選んでみてくださいね。
「楽器買取業者」を利用するメリットと注意点

前の章の徹底比較で、「手間(楽さ)」「スピード」「安心感」の3部門で、フリマやオークションを圧倒していたのが「楽器買取業者」でした。
やっぱり、プロに任せる安心感は大きいですよね。
では、なぜ楽器買取業者はそんなに「楽」で「安心」なのでしょうか?
ここでは、買取業者を利用する具体的なメリットを、さらに深く掘り下げて見ていきたいと思います。
もちろん、良いことばかりじゃありません。
「なんでフリマで売るより安くなっちゃうの?」という素朴な疑問や、「こんな場合は買い取ってもらえないかも」といった、知っておくべき注意点についても、正直に切り込んでいきますね。
これを読めば、「なるほど、こういう仕組みだから業者に頼む価値があるんだな」と、きっと納得してもらえると思います。
メリット1:専門スタッフによる適正な査定額が期待できる
楽器買取業者を利用する最大のメリットは、やっぱりこれ、「楽器の価値を正しく見てくれるプロがいる」という安心感です。
例えば、あなたが持っている楽器が、実はちょっと珍しいビンテージ品だったとします。
もし、それを近所の総合リサイクルショップに持っていったらどうなるでしょう?
そこには楽器の専門家はいませんから、「ふーん、古いギターだね。500円」なんて、とんでもない値段を付けられてしまうかもしれません。
これは、フリマアプリで自分で売る時も同じリスクがあります。
相場を知らずに「1万円くらいかな?」と出品したら、実は10万円の価値があった…なんて、泣くに泣けないですよね。
その点、「楽器専門」をうたっている買取業者には、日々たくさんの楽器を査定している専門スタッフがいます。
メーカー、型番、製造年、シリアルナンバーはもちろん、素人目には分かりにくい「ネックの反り具合」「フレットの残り(消耗度)」「電装系(ピックアップやツマミ)の状態」まで細かくチェック。
その上で、今の市場で「いくらで取引されているか」という最新の相場と照らし合わせて、「適正な査定額」をビシッと提示してくれるわけです。
自分に楽器の知識がなくても、その楽器が持つ本来の価値をちゃんと見抜いてくれる。
これは、何物にも代えがたい大きなメリットだと僕は思います。
メリット2:面倒な手続き(梱包・発送)をお任せできる
前の章でも「手間の塊」と書きましたが、フリマアプリやオークションで、多くの人が一番くじけそうになるポイントが「梱包」です。
正直、楽器の梱包をナメてはいけません。
まず、ギターやベースがすっぽり入る、あの細長くて巨大なダンボールって、普通に生活してたら手に入らないですよね。
買うとなると、それだけで1,000円くらいしたりします。
そして、楽器が輸送中にガタガタ動いたり、衝撃で壊れたりしないように、大量の緩衝材(プチプチとか新聞紙とか)を隙間なく詰める作業。
特にギターのネックは折れやすいので、ヘッド部分が浮くように固定したり…と、かなり気を遣う作業で、時間もすごくかかります。
もう、考えただけで「うわ、面倒くさい…」ってなりませんか?
楽器買取業者の「宅配買取」は、この一番面倒な部分をほぼ丸投げできるんです。
多くの業者が、申し込み後に「無料の宅配キット(梱包セット)」を自宅に送ってくれます。
中には、楽器専用に設計されたダンボールや、緩衝材まで入ってる。
私たちは、説明書を見ながらその箱に楽器を詰めて、あとは運送会社に「集荷お願いしまーす」と電話するだけ。
なんなら、送料も業者が負担(着払い)してくれます。
この「時給換算できない手間」を一切合切カットできるのは、お金には代えられない、とんでもなく大きなメリットだと感じますね。
メリット3:出張買取や宅配買取などライフスタイルに合わせて選べる
買取業者の便利なところは、単に「楽」なだけでなく、「売り方の選択肢が多い」ことにもあります。
大きく分けて、「店舗買取」「宅配買取」「出張買取」の3つですね。
これが、自分の生活スタイルや状況に合わせて選べるのがすごく良いんです。
まず「店舗買取」。
これは、家の近くに信頼できる楽器専門店がある人向け。
楽器を持って行って、査定してもらって、金額にOKすれば、その場で現金ゲット。
この「スピード感」は最大の魅力ですね。
次に「宅配買取」。
これは、日中は仕事で忙しいとか、近所に良い楽器屋がない、という人にピッタリです。
自分の空いた時間に梱包して、コンビニから発送したり、集荷を頼んだりできる。
査定員さんと顔を合わせずに、メールや電話だけで完結する非対面の手軽さも、今どきかもしれません。
そして「出張買取」。
これはもう、「王様スタイル」と呼びたいくらいの楽さです(笑)。
指定した日時に、査定員さんが家まで来てくれる。
玄関先(あるいは部屋の中)で楽器を見てもらって、査定額を聞いて、OKならその場でサインして、楽器はそのまま持って行ってもらえます。
家から一歩も出る必要がない。
このように、自分の都合に合わせて「どう売るか」を選べる柔軟性も、業者の大きな強みですね。
メリット4:大型楽器や複数点のまとめ売りにも強い
メリット3の「出張買取」とも深く関わってきますが、特に「デカい楽器」や「数がめちゃくちゃ多い時」に、買取業者は真価を発揮します。
例えば、あなたが売りたいのが「電子ピアノ」や「ドラムセット一式」、「マーシャルの大型アンプ(スタック)」だったらどうでしょう?
これをフリマアプリで売ろうと思ったら…まず、送料がいくらかかるか見当もつかないですよね。
おそらく、数万円レベルです。
そもそも、どうやって梱包して、どこから発送するの?という話で、ほぼ詰んでしまいます。
こういう時こそ、「出張買取」の出番です。
専門スタッフが2人とかで来てくれて、査定はもちろん、解体や運び出しまで全部やってくれます。
私たちは、文字通り「お疲れ様です」と見送るだけ。
これはもう、フリマやオークションでは絶対に真似できないサービスです。
また、「バンド引退するから、ギター5本とベース2本、エフェクター20個とシールド類とかスタンドとか、全部まとめて処分したい!」みたいな「まとめ売り」の時。
これをフリマで一個一個出品するなんて、考えただけで気が遠くなりますよね。
買取業者なら、「じゃあ、全部まとめて〇〇円ですね」と一括で査定してくれて、一気に引き取ってくれます。
こういう「個人ではどうにもならない規模」の売却に強いのも、業者の大きな魅力です。
注意点:フリマやオークションより買取価格が低くなる傾向とは?
さて、ここまでは良いところばかり見てきましたが、ここからは大事な「注意点」です。
前の章の比較でもあった通り、やっぱり一番気になるのは「買取価格は、フリマの相場より低くなりがち」という点ですよね。
「なんで安く買い叩かれなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、これは別に業者が意地悪をしているわけじゃないんです。
ちょっと冷静に、業者の「ビジネスモデル」を考えてみましょう。
まず、買取業者はボランティアではなく、会社(ビジネス)としてやっています。
彼らがあなたから買い取った楽器は、彼らにとっての「仕入れ商品」になります。
買い取った楽器は、そのまま店頭に並ぶわけじゃありません。
専門のスタッフがキレイにクリーニングして、弦を張り替えて、ネックや弦高を調整して、ガリ(ノイズ)が出れば修理して…と、「次に買う人が安心して使える状態」にメンテナンスします。
そして、自社のお店やネットショップで「中古品」として、次に欲しい人に向けて「販売」するわけです。
この時、業者は「あなたから買い取った価格」と「次に売る価格」の「差額(利益)」で、商売を成り立たせています。
その利益の中から、専門スタッフのお給料や、お店の家賃、テレビCMなどの広告費、そして私たちが無料で使わせてもらっている「宅配キットの送料」や「出張査定のガソリン代」なんかを全部まかなっているんですね。
…こう考えると、業者の買取価格が、個人間取引のフリマ相場(=業者の販売価格に近い)よりも安くなるのは、当たり前だと思いませんか?
その価格差は、面倒な梱包や発送、クレーム対応のリスク、修理やメンテナンスの手間、在庫を抱えるリスク…そういったものを全部まとめて「肩代わり」してもらうための「サービス料」や「手数料」のようなもの、と考えると、すごく納得しやすいんじゃないかなと思います。
注意点:買取不可や大幅な減額査定になるケース
もう一つの注意点は、「どんな楽器でも必ず買い取ってくれるわけじゃないよ」ということと、「最初の見積もりより値段が下がることがあるよ」ということです。
まず、「買取不可」になるケース。
これは、例えば安価なギターのネックがポッキリ折れてしまっているとか、修理するのにお金がかかりすぎて、どう考えても再販できないような状態のものですね。
あとは、あまりにも無名なメーカーの楽器や、おもちゃに近いようなものも、楽器としての価値がつかず、買取を断られることがあります。
もちろん、盗品や、シリアルナンバーが意図的に削られているようなものは、法律的に買い取れません。
次に、「大幅な減額査定」になってガッカリするケース。
これは、Webや電話での「事前査定」と、実物をプロが見る「本査定」で、状態の認識にギャップがあった時に起こりがちです。
例えば、電話で「状態はキレイです」と伝えて、5万円の見積もりが出たとします。
でも、いざ実物を送ってみたら、査定員さんが「あ、これ、ネックが結構反ってますね」「アンプに繋いだらツマミにガリ(ノイズ)が出ますね」と判断した場合。
当然、修理費用がかかるので、本査定額は「3万円です」みたいに下がってしまうわけです。
他にも、専用のハードケースや電源アダプタといった「重要な付属品」が欠品している場合や、タバコのヤニ汚れやペットのニオイが染み付いている場合も、大きな減額対象になりやすいポイントです。
こういうガッカリを防ぐためにも、事前査定の段階で、なるべく正直に「ちょっとガリがあるかも」「少しネックが反ってる気がする」と伝えておくのが、お互いにとって良い結果に繋がるコツかなと思います。
「フリマアプリ(メルカリなど)」で楽器を売るメリットとデメリット

さて、前の章では「楽器買取業者」のメリットと注意点をじっくり見てきました。
「やっぱりプロに任せるのが楽で安心だな」と感じた方も多いと思います。
でも、そうは言っても、やっぱり「フリマアプリ」って気になりますよね。
メルカリやラクマといったサービスです。
第2章の比較では、「手間はかかるしリスクもあるけど、一番高く売れる可能性がある」という、まさに「ハイリスク・ハイリターン(可能性)」な選択肢でした。
ここでは、なぜ多くの人がその「手間」を乗り越えてでもフリマアプリを選ぶのか、その強力なメリットにまず触れていきます。
そして、ここからが本番。
メタキーワードにもある「メルカリ デメリット」の言葉通り、特に「楽器」という商品をフリマで売る際に、どれほどの「落とし穴」が待っているのか。
そのデメリットについて、これでもか!というくらい具体的に、正直に、掘り下げていきます。
この章を読めば、「よし、自分はフリマに挑戦しよう」と思うか、「あ、自分には絶対ムリだ…」と思うか、ハッキリと答えが出るはずですよ。
メリット:自分で価格を決められる(高く売れる可能性)
フリマアプリの最大の魅力、それはもう圧倒的に「価格決定権」が自分にあること、これに尽きると思います。
買取業者の場合、プロが査定した金額が提示されて、私たちは基本的に「はい(売ります)」か「いいえ(売りません)」の二択ですよね。
もちろん、多少の交渉はできるかもしれませんが、その査定額を大きく超えることはありません。
でも、フリマアプリは違います。
「このギター、俺は5万円で売りたい!」と思えば、5万円で出品できるわけです。
買取業者の査定額というのは、前の章でも説明した通り、業者が再販する時の「販売価格」から、業者の「利益」や「メンテナンスコスト」「人件費」などを引いた金額です。
でも、フリマアプリは、その業者の「販売価格」に近い値段で、個人(欲しい人)に直接売ることができる。
だから、例えば買取業者の査定が「3万円です」と言われたギターが、メルカリで「5万円で売れました!」なんていう話は、全然珍しくないんです。
この「うまくいけば、どの方法よりも高く売れる(手残りが多くなる)かもしれない」という期待感。
これが、後述する数々のデメリットを乗り越えさせるほどの、強力な「魔力」であり、最大のメリットなんじゃないかなと感じます。
メリット:スマホ一つで簡単に出品できる手軽さ
もう一つのメリットは、その「出品のハードルの低さ」ですね。
これは本当にすごい革命だと思います。
昔だったら、楽器を売るとなると、重い楽器をえっちらおっちらお店まで持っていくか、パソコンに詳しい人がオークションサイトで複雑なページを作って出品するか、でした。
でも今は、スマホさえあれば、誰でも、今すぐ、出品ができちゃう。
売りたい楽器を、スマホのカメラでパシャパシャと何枚か撮って。
「YAMAHAの〇〇です。学生時代に使ってましたが、最近弾かないので売ります。音出し確認OKです」みたいな説明文をちゃちゃっと書いて。
「うーん、いくらにしようかな…3万円くらい?」と価格を決めて、「出品」ボタンをポチッ。
たったこれだけの作業で、その瞬間から、日本中の「YAMAHAの〇〇を探してた人」に、自分の楽器が届く可能性があるわけです。
この「出品するだけ」なら、めちゃくちゃ手軽、というのも大きな魅力ですよね。
…そうなんです。
あくまで、「出品するだけ」なら、手軽なんです。
本当の大変さは、そこから先に待っています。
というわけで、いよいよ本題のデメリットを見ていきましょう。
【要注意】楽器をメルカリで売る際の大きなデメリット
お待たせしました。
ここからが、メタキーワード「楽器 メルカリ デメリット」の核心部分です。
第2章の比較で、「手間は×(悪い)」「トラブルリスクも×(悪い)」と評価しましたが、なぜそう言い切れるのか。
洋服や本、ゲームソフトを売るのとは、ワケが違います。
「楽器」という商品は、「大きくて、重くて、デリケート」で、なおかつ「専門知識が問われる」という、フリマアプリで扱うには非常に難易度の高い商材なんです。
その具体的な理由を、4つの視点から徹底的に解説します。
覚悟はいいですか?
デメリット1:値下げ交渉やコメント対応の手間
まず、精神的にジワジワくるのが、この「コミュニケーションコスト」です。
特にメルカリは、もはや「文化」と言っていいレベルで「値下げ交渉」が当たり前に行われていますよね。
適正価格で出品したつもりでも、数分後には「コメント失礼いたします。購入を真剣に検討しております。つきましては、〇〇円にお値下げしていただくことは可能でしょうか?」という通知がピロンと鳴ります。
これが、人によってはかなりのストレス。
こちらが送料や手数料を考えてギリギリの値段で出しているのに、「1万円で即決します!」みたいな無茶な要求が来ることも日常茶飯事。
「すみません、出品したばかりなので…」と丁寧に断るのも気を使いますし、かといって無視するわけにもいかず。
また、楽器ならではの「専門的な質問」も来ます。
「ネックの反りは順反りですか?逆反りですか?」
「トラスロッドは、締める方向にも緩める方向にも余裕がありますか?」
「12フレット上での弦高を、6弦側と1弦側でそれぞれ教えてください」
…どうですか?
楽器に詳しくない人は、もうこの時点で「???」ですよね。
こういう質問に答えられなかったり、適当に答えたりすると、今度は「信用できない出品者だな」と思われて売れなくなってしまう。
この、24時間いつ飛んでくるか分からないコメントに、丁寧に対応し続ける「マメさ」と「精神的なタフさ」。
これが無い人には、フリマアプリはかなりしんどい戦場だと思います。
デメリット2:梱包・発送作業が非常に大変(特に大型楽器)
もし、あなたがフリマアプリでの楽器売却を断念するとしたら、たぶん理由の9割はこれです。
断言します。楽器の梱包は、あなたが想像している3倍は大変です。
買取業者が「梱包キット無料」とか「集荷に来てくれる」というサービスをやっているのは、裏を返せば「それくらい面倒でコストがかかる作業」だからなんですね。
まず「梱包材の調達」。
ギターやベースがすっぽり入る、あの細長くて巨大なダンボール(通称:ギター用ダンボール)、近所のスーパーには売ってません。
楽器屋さんで運良くもらえることもありますが、基本的にはネット通販で1,000円〜2,000円くらい出して買うことになります。
次に「緩衝材の準備」。
楽器を衝撃から守るため、大量のプチプチ(エアキャップ)が必要です。
これもホームセンターで買うと、結構な金額になります。
そして「梱包作業」。
ダンボールを組み立てて、楽器をプチプチでグルグル巻きにして、箱の中の隙間という隙間を新聞紙や緩衝材でパンパンに埋めて、楽器が箱の中で1ミリも動かないように固定する。
特にネックは折れやすいので、ヘッド部分が浮くように「ネック枕」を作って固定したり…。
この作業、慣れてない人がやると、平気で1時間以上かかります。
最後に「発送手続き」。
このクソデカい荷物(160サイズ、あるいは170サイズ超えは当たり前)を、受け入れてくれる運送会社(ヤマト便や佐川急便など)の営業所まで、自分で車で運んで持っていくか、家まで集荷に来てもらう手続きをする。
…どうでしょう。
これを「売れた喜びで楽しめる」という人以外には、はっきり言って苦行でしかないと思います。
デメリット3:輸送中の破損によるクレームリスク
デメリット2であれだけ頑張って梱包しても、100%は防ぎきれないのが「輸送事故」です。
特にギターのネックなんて、構造的にすごく弱いですから、運送会社さんがちょっと手荒に扱えば、簡単に「ポッキリ」いきます。
もし、購入者から「届いた!ワクワク!」じゃなくて、「あの…届いたんですけど、ネックが折れてました」という恐怖のメッセージが来たら、どうしますか?
ここからが地獄の始まりです。
購入者は「あなたの梱包が不十分だったから壊れたんだ!返金しろ!」と主張します。
あなたは「いや、あれだけ厳重に梱包したんだから、運送会社が落としたに決まってる!運送会社に言え!」と主張します。
運送会社は「うちのせいだと決まったわけじゃない」と言います。
メルカリの運営事務局も、なかなか間に入ってくれません。
この責任のなすりつけ合い。
最終的に、メルカリ便などの補償が適用されて(適用されないことも多いですが)、売買がキャンセルになったとしても、あなたの手元には「ネックの折れた(価値ゼロの)ギター」だけが戻ってくる…。
もう、最悪ですよね。
他にも、「届いて弾いてみたら、アンプから音が出なかった(輸送中の振動が原因かも?)」とか「説明になかったノイズ(ガリ)が出る」といったクレームも、楽器ならではの「あるある」です。
この「無事に届いて、購入者が『受け取り評価』ボタンを押すまで、一瞬も気が抜けない」という精神的ストレス。
これも、とんでもなく大きなデメリットです。
デメリット4:手数料と送料で「手残り」が少なくなる
メリットの1番目で「高く売れる可能性」と書きました。
でも、あくまで「可能性」であって、必ずしも「手残り」が一番多くなるとは限らないのが、フリマアプリの怖いところです。
ここで、第2章でも触れた「手残り」の計算を、もう一度しっかりやってみましょう。
例えば、あなたがメルカリでギターを 50,000円 で売ることに成功したとします。
「やった!業者の査定は4万円だったのに、1万円も高く売れた!」と喜ぶのは、まだ早い。
まず、ここからメルカリの「販売手数料」が 10% 引かれます。
50,000円 × 10% = 5,000円。
この時点で、あなたの売上は 45,000円 です。
次に、ここから「送料」がかかります。(※「送料込み」で出品した場合)
ギターを安全に送るための送料は、安くても 2,000円〜3,000円 は見ないといけません。
仮に送料が 3,000円 だったとしましょう。
45,000円 – 3,000円 = 42,000円。
これが、あなたの最終的な「手残り」です。
…あれ?
買取業者の査定額は 40,000円(※送料・手数料・梱包材費すべてゼロ)でしたよね。
ということは、あれだけ面倒なコメント対応をして、1時間以上かけて梱包作業をして、輸送破損のストレスに耐えた結果、あなたが余分に得られた利益は、たったの 2,000円 だった、ということになります。
もし、送料が 5,000円 かかるアンプだったら?
手残りは 40,000円 を下回り、「逆転現象」が起きてしまいます。
この「手間」と「リスク」を時給換算して、「2,000円」の差額に価値を見出せるかどうか。
これは、人によって答えがハッキリ分かれるところだと思いますね。
楽器の梱包はどうする?サイズ別の注意点と配送方法
と、ここまで散々デメリットを煽ってきましたが、「それでも俺は挑戦する!」という猛者のために、簡単な梱包と発送のノウハウも紹介しておきます。
これができそうかどうかも、判断基準にしてみてください。
1. ギター・ベースの場合
一番安全なのは、もちろん「ハードケース」に入れて、そのハードケース自体をプチプチでグルグル巻きにして発送することです。
ソフトケースしかない場合や、本体のみの場合は、「ギター用ダンボール」の入手が必須です。
ネット通販(Amazonや楽天、サウンドハウスなど)で1,500円くらいで買えます。
本体をプチプチで巻き、ダンボールに入れたら、ヘッドとボディエンド、ネックの付け根などが箱の中で動かないよう、丸めた新聞紙や緩衝材を「枕」のように詰めて固定します。
配送は、160サイズや170サイズを超えることが多いため、ヤマト運輸の「ヤマト便(※宅急便とは別)」や、佐川急便の「飛脚ラージサイズ宅配便」を使うのが一般的です。
メルカリ便もサイズ上限が拡大しているので(らくらくメルカリ便は160サイズまで、ゆうゆうメルカリ便は170サイズまで、たのメル便は450サイズまで)、事前に確認しましょう。
2. エフェクター(小型)の場合
これは比較的カンタンですね。
元の箱があればベスト。
無ければ、本体をプチプチで(特にツマミが壊れないよう厚めに)包み、小さいダンボール箱に入れます。
宅急便コンパクトや、レターパックプラス(厚さ制限に注意)、あるいは60サイズの宅急便で送れます。
3. アンプ(中型〜大型)の場合
これが実は一番大変かもしれません。
重いので、とにかく「丈夫なダンボール」が必要です。
買った時の元の箱があれば最高ですが、無ければ、スーパーなどで大きくて丈夫なダンボールを2つもらってきて、組み合わせて自作するなどの工夫が要ります。
本体をプチプチで包み、特に四隅(カド)は輸送中にぶつけやすいので、ダンボールを折ったものでガード(コーナーガード)を作ると安全性が高まります。
重量もあるので、送料はかなり高額になることを覚悟しましょう。
「思ったより状態が悪い」を防ぐ商品説明のコツ
最後に、トラブル(デメリット3)を未然に防ぐための、一番大事な自衛策を伝授します。
それは、「商品説明を、これでもかというほど正直に書くこと」です。
絶対に、キズや不具合を隠してはいけません。
「キレイな方が高く売れるかも」というスケベ心は、後で100倍のしっぺ返しになって返ってきます。
目指すのは、「正直すぎる」くらいが丁度いいんです。
1. 全体の写真:まず、表、裏、ヘッド、全体の形がわかる写真を、明るい場所で撮ります。
2. キズ・汚れ・サビ:「ここからマイナスポイントです」と宣言して、ボディの打痕(へこみ)、塗装の剥げ、バックルの擦り傷、金属パーツのサビやクスミなど、全ての箇所を「あえてアップで」撮影します。
そして、「写真〇枚目の通り、ここに打痕があります」「金属パーツにくすみが見られます」と、文章でも全部書きます。
3. ネックの状態:ここが一番モメるところ。
専門家じゃないなら、「素人目ですが、現状で大きな反りは無いように見えます」とか「やや順反り気味かもしれませんが、演奏に支障はありませんでした」など、自信がないことと、自分の主観であることを正直に書きます。
トラスロッド(ネックの中の鉄心)は、知識がないなら「自分では一度も触っていません。左右に余裕があるかは分かりかねます」と書くのが一番安全です。
4. 電装系:「アンプに繋いでの音出し確認済みです」と書くだけで安心感が違います。
もしノイズがあるなら、「ボリュームのツマミを回す際、少しガリ(ジジッというノイズ)が出ることがあります」と正直に書きましょう。
5. 付属品:「写真に写っているソフトケースが付属します」「アーム(棒)はありません」など、何が付いて、何が付かないのかを明確にします。
こうやって「悪いところ」を全部さらけ出すと、神経質な人やクレーマー気質な人は、そもそも買ってきません。
「この状態を全部理解した上で、この値段なら欲しい」という、本当にその楽器を必要としている人だけが購入してくれるようになります。
これが、フリマアプリで精神を消耗しないための、最大のコツですよ。
「ネットオークション(ヤフオクなど)」で楽器を売るメリットと相場の実態

さて、いよいよ3つ目の方法、「ネットオークション」です。
ヤフオク(Yahoo!オークション)なんかが昔から有名ですね。
前の章で解説した「フリマアプリ」と、自分で出品して、個人に売る、という点ではすごく似ています。
じゃあ、何が決定的に違うのか?
それは、フリマアプリが「出品者が決めた価格」で売る(あるいは値下げ交渉で売る)のに対して、オークションは「欲しい人が価格を競り合って」値段が決まる、という点です。
そう、「競り合い」。
ここに、オークションならではの「ロマン」と「うまみ」が詰まっているんですね。
ですが、もちろんフリマアプリと同じ、いや、人によってはそれ以上に感じる「デメリット」も抱えています。
そして、メタキーワードにもある「楽器 オークション 相場」という、みなさんが気になるであろう「じゃあ、いくらで売れるの?」という相場の実態。
その仕組みについても、この章でじっくりと解説していきますね。
フリマとどっちがいいか悩んでいる人は、ぜひこの違いを比べてみてください。
メリット:希少価値の高い楽器は価格が高騰しやすい
オークションを選ぶ最大の理由、それはもう「価格高騰の可能性」これに尽きると思います。
どういうことかと言うと、フリマアプリって、基本的には「出品者が決めた価格」が上限ですよね。
5万円で出品したら、5万円で売れるか、あるいは値下げ交渉で4万8千円になるか、です。
でも、オークションは「欲しい人が出せる金額」が上限になります。
もし、あなたが売ろうとしている楽器が、とっくに生産終了している「ビンテージ品」だったり、数量限定の「アーティストモデル」だったり、市場にめったに出てこない「希少品」だったとしたら?
フリマアプリで「相場が分からないから、とりあえず5万円かな」なんて出品したら、本当は10万円の価値があったとしても、5万円でサクッと売れて「損」をしてしまうかもしれません。
でも、オークションなら違います。
そういう「お宝」を探しているマニアやコレクターが、日本中から(時には海外からも!)その出品ページを見つけ出します。
そして、「お、これ探してた!5万円か、俺は6万出す」「なに、6万だと?こっちは7万だ!」「8万!」…と、欲しい人同士が自動的に競り合って、価格を吊り上げていってくれるんです。
結果として、業者の査定額やフリマの想定価格を、はるかに超える「思わぬ高値」がつく可能性がある。
これこそが、オークションの最大の醍醐味(だいごみ)であり、メリットですよね。
メリット:最低落札価格を設定できる安心感
オークションには、「1円スタート!」みたいに、すごく安い金額から始めて注目を集める出品方法があります。
でも、これって怖いですよね。
「もし、誰も入札しなくて、100円とかで落札されちゃったらどうしよう…」って。
その不安をバッチリ解消してくれるのが、「最低落札価格」という機能です(※ヤフオクだと有料オプションだったりします)。
これは、出品する時に「自分は、最低でも3万円以上じゃないと売る気はありませんよ」というラインを、入札者からは見えないように設定できる仕組みです。
入札者はどんどん競り合いますが、もしオークション終了時に、最高入札額が2万8千円だったら、「最低落札価格に達しなかったため、落札者なし」として終了します。
これがあれば、「1円スタート」で注目を集めつつ、「安く買い叩かれるリスク」をゼロにできるわけです。
この安心感は大きいですよね。
あと、個人的には、フリマアプリ特有の「値下げ交渉」のやり取りが一切ないのも、精神的にラクだと感じます。
オークションのルールは明快です。
「決まった期間内に、一番高い値段をつけた人が、その値段で買う」。
シンプルですよね。
あの「コメント失礼します…」のやり取りが面倒だと感じる人には、オークションの仕組みの方が合っているかもしれません。
デメリット:出品~入金までの時間が長い
さて、ここからはデメリットです。
前の章の「スピード」比較でも触れましたが、3つの方法の中で、オークションがダントツで「現金化まで時間がかかる」方法です。
これはもう、仕組み上どうしようもありません。
まず、フリマアプリは「即購入」があるので、出品して1分で売れる可能性もあります。
でも、オークションは「競り合い」のための期間が絶対に必要です。
みんなが出品ページを見つけて、悩んで、入札するための時間ですね。
一般的には、この出品期間(ウォッチリストに登録してもらったり、入札を待つ期間)を「5日間」とか「7日間」に設定します。
この時点で、まず約1週間かかります。
そして、オークションが無事に終了して、落札者が決まったとします。
でも、ここからがまた長い。
まず「落札者からの連絡待ち」。
次に「落札者が支払い手続きをするのを待つ」。
コンビニ払いとかだと、さらに数日待つこともあります。
「入金を確認」したら、あなたが「梱包して発送」します。
そして最後に「商品が相手に届いて、相手が『受け取り連絡』ボタンを押す」まで、売上金が確定しません。
…どうでしょう。
出品を開始してから、実際に自分の銀行口座にお金が振り込まれるまで、早くても1週間、通常は10日~2週間くらいは見ておいた方がいいです。
「引っ越しが明後日!」みたいな、スピードを求める人には絶対に向いていない方法ですね。
デメリット:フリマアプリ同様、梱包・発送の手間が大きい
そして、もう一つの大きなデメリット。
前の第4章で、フリマアプリのデメリットとして「梱包・発送作業が非常に大変」と、散々お伝えしましたよね。
あのデメリット、オークションにも「全く同じように」当てはまります。
むしろ、もっと大変かもしれません。
ギター用の巨大なダンボールをどこかで調達してきて、大量の緩衝材(プチプチ)を買ってきて、1時間以上かけて厳重に梱包して、そのデカい荷物を運送会社に持ち込むか、集荷を依頼する…。
この一連の「手間の塊」は、オークションでもそっくりそのまま、自分でやる必要があります。
しかも、ヤフオクの場合、メルカリの「らくらくメルカリ便」のような、匿名配送や全国一律送料の便利な配送サービスが、楽器のような大型商品(160サイズ超え)に対応していないケースも多いんです。
そうなると、自分でヤマト便や佐川急便を手配して、落札者の住所(例えば北海道や沖縄)までの送料を調べて、「送料は〇〇円になります」と連絡して…と、フリマ以上に面倒な手続きが発生する可能性すらあります。
輸送中の破損リスクや、クレームのリスクもフリマアプリと全く同じです。
この「手間」と「リスク」は、フリマもオークションもイコールだと考えておいてください。
楽器オークションの「相場」はどう決まる?
さて、ここでメタキーワードにもあった「楽器 オークション 相場」について、その実態を解説したいと思います。
「オークションの相場って、いくらなの?」と聞かれても、実はすごく答えにくいんです。
なぜなら、フリマアプリでいう「相場」と、オークションでいう「相場」は、意味合いがちょっと違うからなんですね。
フリマアプリの「相場」っていうのは、例えばメルカリで検索して、「あ、このギター、大体3万円前後でよく売れてるな」という「売買が成立しやすい価格帯」のことを指すことが多いです。
でも、オークションの「相場」は、そういう「決まった価格帯」ではありません。
オークションの価格、つまり落札額は、たった一つのシンプルな原理で決まります。
それは、「その楽器を欲しい人が、最終的にいくらまで競り合ったか」という「結果そのもの」です。
例えば、あなたが1万円で出品したギター。
もし、それを欲しい人が日本中に一人もいなければ、入札はゼロ。売れません(相場ゼロ)。
もし、欲しい人が一人だけいたら、その人は1万円で落札します(相場1万円)。
もし、欲しい人が二人いて、Aさんは「5万円までなら出す」と思い、Bさんは「5万1千円までなら出す」と思っていた場合。
二人が競り合った結果、Aさんが5万円で入札したのを、Bさんが5万1千円で上回った時点で、Aさんは脱落します。
結果、この楽器の「相場」は、5万1千円になるわけです。
このように、オークションの相場は「需要と供給のバランス」だけで決まる、非常に流動的なものなんですね。
相場が上がる要因:希少性、人気ブランド、状態の良さ
じゃあ、その「相場(落札価格)」を吊り上げる、つまり「欲しい!」と思う人を増やす要因は何かというと、これはかなりハッキリしています。
まず、なんといっても「希少性」。
これがオークションでは最強のカードです。
生産が終了した「廃盤モデル」、数量限定だった「シグネイチャーモデル(アーティストモデル)」、あるいは70年代の「ジャパンビンテージ」など、とにかく市場に出回っている「玉数」が少ないもの。
こういうのは、探しているコレクターが血眼になってウォッチしています。
次に、「人気ブランド」。
やはり、ギブソン、フェンダー、マーチン、ポール・リード・スミス(PRS)といった王道の人気ブランドは、それだけで「欲しい」と思う人の母数が大きいです。
入札者が集まりやすいので、価格も上がりやすい傾向がありますね。
そして、「状態の良さ」。
同じモデルであっても、「キズひとつない美品」とか「ほぼ新品同様」、あるいは「一切改造されていないフルオリジナル状態」といったものは、高値がつきやすいです。
最後に、「付属品の完備」。
買った時に付いてきた「専用のハードケース」や「保証書」「認定証」「アーム」なんかが全部揃っていると、特にコレクターからの評価が上がり、入札価格も上がります。
これらの「希少性」「人気」「状態」「付属品」といった要素が重なれば重なるほど、入札合戦がヒートアップして、相場(落札価格)は青天井で上がっていく可能性があるわけです。
相場が下がる要因:ジャンク品扱い、付属品の欠品
逆に、相場が上がらない、つまり入札が入らないか、安値で終わってしまう要因も見ておきましょう。
一番分かりやすいのは、「状態の悪さ」ですね。
例えば「音が出ません」とか「ネックが折れています」といった、いわゆる「ジャンク品」。
これは当然、価格は低くなります。
…ただ、ここがオークションの面白いところで、フリマや買取業者では「価値ゼロ(買取不可)」と言われたジャンク品でも、オークションなら「自分で修理できる人」や「パーツ取り」を目的とした人が入札してくれることがあるんです。
だから、「壊れてるからゴミ」と諦める前に、ダメ元でオークションに出してみると、数千円になる可能性は秘めています。
次に、「付属品の欠品」。
特に、そのモデル専用のハードケースとか、フロイドローズ(特殊なブリッジ)のアームとか、後から手に入れるのが難しい付属品が欠品していると、相場はガクッと下がります。
あとは、単純に「不人気・マイナーブランド」。
どれだけ状態がピカピカでも、そもそも「欲しい」と思う人が日本にいなければ、入札は入りませんよね。
そして、意外と見落としがちなのが「説明文や写真の不足」です。</
モノは良いはずなのに、出品ページの写真が暗くてよく見えなかったり、説明文が「ギターです。使わないので売ります」の一言だけだったりすると…。
入札する側は「これ、なんか隠してるんじゃないか?」「状態が悪いのかな?」と不安になります。
この「不安」が、入札を控える大きな理由になり、結果として相場が上がらないんです。
オークションで高値を狙うための出品テクニック
さて、デメリットや相場の実態を理解した上で、「よし、俺は希少品を持ってるからオークションで高値を狙うぞ!」という人のために、フリマとはちょっと違う「オークションで勝つためのコツ」をいくつか紹介します。
まず、悩むのが「開始価格の設定」です。
「1円スタート」にすると、ウォッチリスト登録数やアクセス数が爆発的に増えるので、人気商品なら最終的にかなり高騰しやすいです。
でも、もし不人気だったら…というリスクが怖い人は、先ほど紹介した「最低落札価格」を設定するか、最初から「この値段なら売ってもいい」という、ある程度強気な価格(例:3万円スタート)にするのが無難です。
次に、これがオークションでは「最重要」と言ってもいいテクニック、「終了日時の設定」です。
オークションは、終了間際のラスト10分で価格が一番動きます。
ということは、その「終了時刻」に、一番たくさんの人がパソコンやスマホの前にいる時間帯を狙うべきなんです。
それは、ずばり「日曜日の夜(21時〜23時の間)」。
ここがゴールデンタイムです。
逆に、平日の真っ昼間とか、金曜の夜(みんな飲みに行ってる)とかに終了時刻を設定するのは、高値で売りたいなら絶対にやめた方がいいですね。
そして「写真と説明文」。
これはフリマの章でも言いましたが、オークションはもっとシビアに見られます。
写真は、使える枚数(ヤフオクなら10枚)をフルに使って、あらゆる角度から(キズやサビも含めて)撮影します。
説明文は、「正直に」書くのは当然として、もし知識があるなら、その楽器の「魅力」や「歴史」を付け加えると効果的です。
(例:「〇〇年製のモデルで、この時期特有の太いネックから出るサウンドが魅力です」とか「機材整理のため、泣く泣く出品します」みたいな)
最後に「タイトル」。
検索で見つけてもらえないと意味がないので、メーカー名(Fender)や型番(Stratocaster)はもちろん、「ビンテージ」「ジャパンビンテージ」「美品」「レア」「即決」など、探している人が検索窓に打ち込みそうなキーワードを、許される文字数ギリギリまで詰め込むのがセオリーですよ。
楽器を少しでも高く売るために知っておきたい5つのコツ

さて、ここまでの章で、「楽器買取業者」「フリマアプリ」「ネットオークション」という3つの主要な売り方を、それぞれのメリット・デメリットで徹底的に比較してきました。
「よし、自分は手間を考えて業者にしよう」とか、「いや、やっぱり高値を狙ってフリマに挑戦だ」とか、ご自身の方向性がある程度定まってきたんじゃないかなと思います。
そこでこの章では、視点をガラッと変えます。
どの方法を選ぶにしても、全員に共通して使える、「じゃあ、どうすればその楽器の価値を1円でも高くできるの?」という、具体的な5つのコツをご紹介します。
これ、本当に大事です。
ほんのちょっとの手間をかけるか、かけないか。
それだけで、査定額や落札価格が数千円、モノによっては数万円変わってくることもザラにありますからね。
あなたが大切にしてきた楽器を、一番納得できるかたちで次の人にバトンタッチするために、ぜひ実践してほしい5つのポイントです。
順番に見ていきましょう。
コツ1:売る前に必ず清掃・簡単なメンテナンスを行う
まず、一番基本的でありながら、一番効果が出やすいコツがこれ、「キレイに掃除すること」です。
考えてみてください。
もしあなたが中古車を買うとして、ピカピカに洗車された車と、泥だらけでホコリまみれの車、どっちに高い値段をつけますか?
…言わずもがな、ですよね。
楽器も全く同じです。
査定する業者さんも、フリマで写真を見る購入者さんも、同じ人間です。
「第一印象(見た目)」は、査定額にものすごく大きな影響を与えます。
ケースを開けた瞬間、ホコリが積もっていたり、ボディが指紋でベタベタだったり、ステッカーがベタベタ貼られたままだったりすると…。
「うわ、これは大切に扱われてこなかったんだな」「きっと、見えない部分(ネックの反りとか電装系)も状態が悪いんだろうな」と、無意識のうちにマイナスの印象を持たれてしまいます。
これは、大きな損です。
何も「壊れたところを修理しろ」と言っているんじゃありません。
ほんの30分でいいので、「清掃」をしてあげるだけです。
楽器用の柔らかいクロスで、ボディやヘッドの指紋、汚れを優しく拭き取ってあげる。
ブリッジやペグ(糸巻き)といった金属パーツがくすんでいたら、軽く磨いてあげる。
もし可能なら、フレット磨き専用のクロスやコンパウンド(数百円で買えます)で、フレットをキュキュッと磨いてみてください。
ここがピカピカに光るだけで、ギターは驚くほど「新品同様」の顔つきに戻ります。
指板(ネックの表面)も、専用のオイル(レモンオイルなど)で軽く汚れを落として保湿してあげると、見違えるようにキレイになりますよ。
こういう「愛情を込めた清掃」の跡が見えるだけで、「ああ、この人は楽器を大事にしてたんだな」という信頼感が生まれ、査定員さんも「じゃあ、こちらも頑張って良い値段をつけよう!」という気持ちになってくれるものです。
やるとやらないとでは、大違い。絶対にやった方がいいコツNo.1ですね。
コツ2:付属品(ケース、保証書、エフェクターなど)を揃える
2つ目のコツは、「付属品をできる限り揃えること」です。
「買った時に、箱の中に入っていたもの」を全部集める、ということですね。
特に、楽器買取業者やオークションのマニアな人たちは、「完品(かんぴん)かどうか」、つまり新品の時と同じセット内容が揃っているかを、すごく重要視する傾向があります。
付属品が欠けていると、それだけで「減額対象」になってしまうんですね。
じゃあ、「付属品」って具体的に何でしょうか?
一番大事なのは、「専用のケース」です。
それがハードケースであれ、ソフトケース(ギグバッグ)であれ、買った時に付いてきた純正のケースが有るか無いかで、査定額が数千円、場合によっては数万円変わることもあります。
特に、ギブソンやマーチンみたいな高級ブランドの「純正ハードケース」は、それ単体でものすごい価値がありますからね。
他には、
・保証書やマニュアル(取扱説明書)
(保証期限が切れていても、それが「正規品である証明」になるので大事です)
・トレモロアーム(ギターのブリッジに付ける棒ですね)
(これが無いと、地味に大きな減額になります)
・調整用の六角レンチなど、付属してきた工具類
・(限定モデルの場合)シリアルナンバー入りの認定証
あと、エフェクターやシンセサイザー、MTR(録音機器)などで特に重要なのが、「専用の電源アダプター」です。
「アダプターは汎用品を使ってたから、純正のはどっかいっちゃった」というのは、最悪の場合「動作確認ができませんね」とジャンク品扱いにされたり、大幅な減額になったりする原因No.1です。
「楽器を売ろう」と決めたら、査定に出す前にまず、押入れやクローゼット、物置のダンボールの中を大捜索してみてください。
「あ!こんなところにアームがあった!」とか「保証書一式、ここに入れてたわ!」という発見は、文字通り「お金を発見した」のと同じくらいの価値がありますよ。
コツ3:弦や消耗品は交換すべき?そのままで良い?
これも、すごくよく悩むポイントだと思います。
「弦がサビサビなんだけど、これ、新しいのに張り替えた方がいいのかな?」って。
これに対する僕の答えは、「売る方法によって、答えが変わります」です。
まず、【楽器買取業者に売る場合】。
この場合は、結論から言うと「弦を張り替える必要は全くありません」。
むしろ、張り替えたら損です。
なぜかと言うと、買取業者は、買い取った楽器を「商品」として店頭に出す前に、必ず自社でリペアマンがクリーニング、メンテナンス、そして「新品の弦への張り替え」をルーティンとして行うからです。
こっちが1,000円出して新品の弦に張り替えて査定に出しても、業者は「あ、どうせウチでまた張り替えるんで」としか思いません。
査定額が1,000円上がることは、まず無いでしょう。
つまり、その1,000円は丸々ムダになってしまうんですね。
弦がどれだけサビていようが、汚れていようが、業者は「交換前提」で見ているので、気にせずそのまま査定に出しちゃいましょう。
(もちろん、サビでフレットが削れてるとかは別問題ですが)
次に、【フリマアプリやオークションに売る場合】。
こっちは、正直ちょっと悩ましいです。
ただ、僕個人の意見としては、「張り替えた方がベター(良い)」かもしれません。
なぜなら、買い手が「プロの業者」ではなく、「素人の個人」だからです。
彼らにとっては、前のコツでも言った「第一印象(見た目)」がすべて。
出品されている楽器の写真を見た時、弦がピカピカに輝いていたら、「おお、キレイだな!」「ちゃんとメンテナンスされてる楽器だな」と、すごく良い印象を持ちますよね。
購買意欲がグッと上がります。
逆に、弦が真っ黒に汚れていたり、赤茶色にサビていたりしたら、どうでしょう。
それだけで「うわ、汚い…」「なんか状態悪そう」「買うのやめとこう」と、敬遠されてしまう可能性が高いです。
もちろん、「どうせ自分の好きなゲージ(太さ)の弦に張り替えるから、そのままでいいよ」という買い手も多いので、必須ではありません。
ですが、「売れやすさ」や「印象」を少しでも良くしたいなら、フリマ・オークションに限っては、張り替えておく価値はあるかな、と思いますね。
コツ4:楽器の「売り時」はいつ?(モデルチェンジ前など)
洋服に「売り時」があるように、楽器にも「高く売れるタイミング」というものが存在します。
一番分かりやすく、そして重要なのが、「モデルチェンジの直前」です。
これは特に、ギターそのものより、シンセサイザーやマルチエフェクター、オーディオインターフェースといった「デジタル機器」に強く当てはまります。
例えば、大人気のマルチエフェクター「A」を使っているとします。
ネットの噂で「そろそろ後継機のBが出るらしい」という情報が流れ始めたら、それが「売り時」です。
もし、後継機「B」が正式に発表されてしまった瞬間、みんなが「B」に飛びつくので、旧型「A」の中古相場は一気に値崩れを起こします。
「まだ噂レベル」のうちに、欲しがっている人がたくさんいる間に売ってしまうのが、高値を維持する最大のコツですね。
他にも、季節的な需要もあります。
一般的には、新学期(4月)や新生活が始まる直前の「2月~3月」や、ボーナスが支給される「6月~7月」「11月~12月」は、楽器を始めよう、買い替えようという人が増える時期です。
中古市場全体が活発になるので、買い手が見つかりやすく、売れやすいタイミングと言えますね。
最近だと、特定のバンドのアニメが流行ったり、有名アーティストがテレビで使ったりすると、そのモデルの相場が急に高騰する、なんていう現象もあります。
…と、まぁ色々なタイミングを挙げましたが、僕が思う「最も大事な売り時」は、たったひとつです。
それは、「あ、この楽器、もう弾かないな」とあなたが決意した、「今、その瞬間」です。
楽器は、実は「弾かずに放置しておく」のが一番状態が悪くなります。
久しぶりにケースを開けたら、ネックが反ってしまっていたり、金属パーツがサビだらけになっていたり、電装系がガリガリになっていたり…。
押入れで眠らせている間にも、その楽器の価値はどんどん下がっていっているんです。
「いつか売ろう」と放置してコンディションが悪化し、査定額が1万円下がるより、「弾かない」と決めた今の良いコンディションのうちに売る。
それが、結果的に一番の「高値」に繋がるんだと思います。
まさに「思い立ったが吉日」ですね。
コツ5:複数の方法で見積もり・相場を必ず比較する
さて、5つのコツの最後。
これがもう、お金の面で言えば「一番重要です」と断言できます。
それは、「必ず、複数の方法で見積もりと相場を比較すること」。
「相見積もり(あいみつもり)」ってやつですね。
例えば、あなたが引っ越しや、車の売却をする時、1社だけに見積もりを頼んで「はい、じゃあそこでお願いします」なんて、決めないですよね?
絶対に、A社、B社、C社と、最低3社くらいは見積もりを取って、一番安い(あるいは一番高い)ところを選びます。
楽器を売る時も、これをやらないのは、本当に、本当にもったいないです。
「近所にあった楽器屋Aに持っていったら、3万円って言われたから、まぁそんなもんかと思って売っちゃった」
…これは、一番やってはいけないパターンです。
もしかしたら、楽器屋Bなら3万5千円、ネット宅配買取のC社なら3万8千円の値段がついたかもしれないのに。
その「比較」という、たった1時間のひと手間を惜しんだせいで、8千円も損をしてしまっているわけです。
じゃあ、具体的にどう「比較」すればいいか。
僕がおすすめする、絶対に損をしないための手順はこうです。
【手順1】
まず、フリマアプリ(メルカリの「売り切れ」検索)や、オークションサイト(ヤフオクの落札相場がわかる「オークファン」など)で、自分が売ろうとしている楽器が、だいたいいくらで「個人間取引」されているのか、その「上限の相場」を把握します。
【手順2】
次に、楽器買取業者の「オンライン査定」や「宅配査定」を、最低でも3社(A社、B社、C社)に申し込みます。
【手順3】
数日後、A社「3万円」、B社「3万5千円」、C社「3万2千円」と、各社の査定額が出揃います。
【手順4】
ここで初めて、あなたは「最強の比較カード」を手に入れたことになります。
「個人間取引の上限相場(例:5万円)」と、
「業者の最高買取額(例:3万5千円)」
この2つを天秤にかけて、「1万5千円の差額のために、フリマの面倒な梱包とクレームリスクを取るか?」それとも「手間もリスクもゼロで、確実に3万5千円をゲットするか?」を、あなたが選べるわけです。
この「比較」というステップさえ踏んでおけば、「B社に売れば3万5千円になったのに、知らずにA社に3万円で売って5千円損した…」という、最悪の事態だけは100%避けられます。
この「ひと手間」を惜しまないこと。
これが、知識やテクニック以上に、一番確実で、一番賢く、一番高く売るための最大の秘訣だと、僕は思いますよ。
後悔しない「楽器買取サービス」の賢い選び方 3つのポイント

さて、これまでの徹底比較で、「楽器を売るならどこがいい?」という問いに対して、一つの答えが見えてきたんじゃないかなと思います。
もちろん、手間とリスクを承知で高値を狙うなら「フリマ」や「オークション」という選択肢もあります。
でも、「楽器の知識に自信がない」「梱包や発送が面倒」「トラブルは絶対に避けたい」…そう考えた時、やはり「楽器買取サービス」に任せるのが、一番現実的で「楽で、早くて、安心」な最適解だと言えそうですよね。
しかーし。
ここで次の悩みが出てきます。
「じゃあ、どこの業者に頼めばいいの?」
今、ネットで「楽器 買取」と検索すれば、それこそ星の数ほどの業者がヒットします。
「どこが一番高いの?」「どこが安心なの?」と、また迷ってしまいますよね。
この業者選びを間違えてしまうと、「有名なところだと思ったのに、めちゃくちゃ安く買い叩かれた…」とか、「対応が悪くて嫌な思いをした…」なんて、後悔するハメになりかねません。
そこでこの章では、あなたが後悔しないために、「本当に信頼できる、納得のいく買取業者」を見極めるための、絶対に外せない「3つの選定ポイント」を具体的に解説していきます。
この基準さえ知っておけば、大きな失敗は避けられるはずですよ。
ポイント1:「楽器専門」の査定員が在籍しているか
もう、これが一番重要だと言っても過言ではありません。
あなたが売ろうとしているのは、洋服や本ではなく、「楽器」という非常に専門性の高いモノだということを、もう一度思い出してください。
その価値は、素人目には到底分かりません。
世の中の買取業者には、大きく分けて2種類あります。
一つは、「なんでも買います!」と謳っている「総合リサイクルショップ」。
もう一つは、「楽器のことならお任せください!」という「楽器専門の買取店」です。
あなたが選ぶべきは、絶対に後者の「楽器専門店」です。
なぜなら、総合リサイクルショップにいる査定員は、残念ながら楽器の知識を持っていない(あるいは、すごく浅い)ことがほとんどだからです。
彼らのマニュアルでは、「ギブソン」や「フェンダー」は有名だから知っていても、あなたが大切にしてきた「Tokaiのジャパンビンテージ」や「Bacchusの限定モデル」の価値は分かりません。
結果、「よくわからないメーカーのギター」として、一律「3,000円」みたいな、悲しい査定額を提示されてしまう危険性が非常に高いんです。
一方、「楽器専門店」には、日々何百本という楽器に触れ、修理し、相場をチェックしている「プロの査定員」が必ず在籍しています。
彼らは、あなたが何も言わなくても、「お、これは〇〇年のモデルですね。この時期の木材は良くて…」「ネックの反りも問題ないし、フレットも8割残ってますね」と、その楽器の「本当の価値」を正確に見抜いてくれます。
そして、その価値にふさわしい「適正な市場価格」を提示してくれるわけです。
業者を選ぶ第一歩は、その業者のホームページをしっかり見て、「楽器専門」と堂々と掲げているか、「経験豊富な専門査定員が在籍」といった言葉がハッキリと書かれているかを確認すること。
これが、買い叩かれないための最低条件ですね。
ポイント2:買取方法(出張・宅配・店舗)が選べるか
2つ目のポイントは、「買取方法の選択肢が多いか」です。
これは、その業者の「規模」や「体力」、そして「利用者への配慮」を測るための、すごく分かりやすいバロメーターになります。
信頼できる大手の楽器買取業者は、ほぼ例外なく、
1. お店に直接持っていく「店舗買取」
2. 楽器を送るだけの「宅配買取」
3. 家まで来てもらう「出張買取」
この3つの買取方法を、ちゃんと用意してくれています(最低でも、宅配と出張は選べるはずです)。
なぜこれが重要かというと、第3章のメリットでも触れた通り、売りたいあなたの「状況」によって、ベストな方法が全然違ってくるからです。
例えば、「家の近所にその店がある。今日、今すぐ現金が欲しい!」という人は、「店舗買取」が最強です。
でも、「地方に住んでいて、近くに専門店がない」とか「日中は仕事で忙しくて、査定に付き合う時間がない」という人は、「宅配買取」が便利ですよね。
そして、「売りたいのが電子ピアノやドラムセット」だったり、「アンプが重すぎて運べない」「ギターが10本あって、まとめて見てほしい」という人は、家まで来てくれる「出張買取」以外、選択肢がないわけです。
もし、ある業者が「ウチは店舗買取しかやってません」だったら、大型楽器を売りたい人はその時点でお手上げです。
「ウチは宅配買取だけです」だったら、今すぐ現金が欲しい人はニーズを満たせません。
この3つの選択肢を全部用意できるというのは、それだけ様々な顧客のニーズに応えようとする「企業の体力」があり、信頼できる証拠とも言えます。
もちろん、私たち利用者にとっても、「自分の状況に合わせて、一番楽な方法を選べる」という、シンプルで大きなメリットになりますよね。
ポイント3:手数料(送料・査定料・振込手数料)が無料か
3つ目は、お金に直結するシビアな話、「手数料」です。
いくら査定額が高くても、そこから「あれも引きます」「これも引きます」と、色々な名目で手数料を引かれてしまったら、最終的な「手残り」はガクッと減ってしまいます。
その点、優良な楽器買取業者の多くは、「査定にかかる費用は、すべてウチが負担します!」という「完全無料」のスタンスを明確に打ち出しています。
あなたが業者選びをする際に、最低限チェックすべき「無料」の項目は、主に以下の5つです。
1. 査定料(鑑定料):
これは当たり前ですね。プロに見てもらうためのお金。これが有料の業者は、まず選ぶ価値がありません。
2. (宅配買取の)送料:
楽器を業者に送る時の片道の送料です。これが「お客様負担」だと、査定額からいきなり2,000円とか3,000円を引かれることになり、大損です。
3. (宅配買取の)梱包キット代:
ダンボールや緩衝材を、無料で自宅に送ってくれるかどうか。これも地味に大事です。
4. 振込手数料:
査定額に合意した後、あなたの銀行口座にお金を振り込む際の手数料(数百円)です。これを「お客様負担」にするセコい業者も、中にはいます。
5. (出張買取の)出張料・交通費:
家まで来てもらうための費用。これも当然、無料でないと困りますよね。
これらの「〇〇手数料」が一つでも「お客様負担」となっている業者は、パッと見の査定額が高く見えても、要注意です。
必ず、業者のホームページの「買取の流れ」や「よくある質問」のページを隅々まで確認して、「査定に関する費用は一切無料」とハッキリ書かれている、明朗会計な業者を選ぶようにしましょう。
それが、最終的な「手残り」を最大化するための、賢い選択です。
総合リサイクルショップより楽器専門店が良い理由
ポイント1の「専門性」で触れましたが、ここは本当に大事なところなので、もう少しダメ押しで深掘りさせてください。
「家の近所に、歩いていける大手のリサイクルショップがあるんだよね。宅配とか面倒だし、そこでいいかなぁ」
…その気持ち、すごく分かります。
でも、もしあなたがその楽器を少しでも大切に思っているなら、その選択は「お待ちください!」と全力で止めたいです。
なぜ、総合リサイクルショップがダメなのか。
理由は明確です。
まず、さっきも言った通り「査定員が素人」だということ。
楽器の価値が分からないので、あなたの楽器が持つ希少性やコンディションの良さが、価格に反映されることはありません。
むしろ、「よく分からないけど、まぁ音は出そうだから」という理由で、不当に安い「一律価格」で買い叩かれるのがオチです。
次に、「メンテナンス体制がない」こと。
リサイクルショップは、買い取った楽器を修理・調整する専門技術を持っていません。
だから、もしあなたの楽器に「ちょっとツマミを回すとガリ(ノイズ)が出る」とか「ネックが少し反っている」といった、専門店なら簡単に直せる程度の不具合があったとしても、リサイクルショップは「あ、これ壊れてますね。ジャンク品です」と判断します。
結果、「買取不可(0円)」か、タダ同然の値段になってしまうんです。
最後に、「販売ルートが弱い」こと。
彼らは楽器を専門に扱っていないので、買い取った楽器を高く売るための「販路」を持っていません。
高く売る自信がないから、当然、仕入れである「買取価格」も、思いっきり低く抑えざるを得ないわけです。
…もう、お分かりですよね。
「楽器専門店」は、これら全てが真逆です。
「査定員はプロ」だし、「自社でリペア(修理)」できるし、「国内外への強力な販売ルート」も持っている。
だから、多少の不具合は「修理前提」でちゃんと買い取ってくれるし、その楽器の価値に見合った「高い査定額」を提示できるんです。
近所のリサイクルショップに持っていく「手間」も、楽器専門店に「宅配買取」を頼む「手間」も、トータルで見たら大差ありません。
でも、出てくる査定額は、下手したら数倍、数万円の差が開くことも普通にあります。
どちらを選ぶべきか、答えはもう明らかだと思いますよ。
査定額に納得いかない場合のキャンセル・返送料を確認しよう
さて、ここまでの3つのポイント(専門性、利便性、手数料無料)をすべてクリアした、優良そうな楽器買取業者を見つけたとします。
これで安心!…と、申し込みボタンを押す前に、もう一つだけ、必ず確認してほしい「最後の落とし穴」があります。
それは、「もし、査定額に満足できなかった場合の、キャンセル料と返送料」についてです。
これは特に「宅配買取」を利用する時に、めちゃくちゃ重要になります。
流れを想像してみてください。
あなたは、良さそうなA社にギターを梱包して送りました(送料はA社負担)。
翌日、A社から電話が来て、「査定結果が出ました。1万円です」と言われました。
あなたは「えっ、安すぎる!それならフリマで売るから、やっぱり返してください」と伝えます。
この「キャンセル」自体は、ほとんどの優良業者が「無料」で受け付けてくれます。
問題は、ここからです。
その「ギターを返送してもらうための送料(返送料)」は、A社が負担してくれる(元払い)のか、それともあなたが負担する(着払い)のか?
もし、このA社が「キャンセル時の返送料は、お客様のご負担となります」というルールの業者だったら、どうなるでしょう。
あなたは、1万円で売るのを諦めたとしても、自宅にギターが戻ってきた時に、運送会社に「着払い送料 2,500円です」と、現金を支払わなければならなくなります。
それが嫌だから、「うぅ…送料2,500円払うくらいなら、仕方ない。1万円で売ります…」と、本当は納得していない安い査定額を、泣く泣く飲むハメになってしまう。
これって、最悪ですよね。
こういう事態を避けるために、申し込みをする前に必ず、業者のホームページの隅々までチェックして、「査定額にご納得いただけなかった場合の、キャンセル料・返送料もすべて無料」と、ハッキリ明記している業者を選んでください。
そこまで確認できて初めて、「リスクゼロ」で、「安心して査定を試せる」業者だと言えるんです。
まとめ:自分に合った方法で大切な楽器を納得して手放そう
「楽器を売るならどこがいい?」という、誰もが悩むテーマについて、「楽器買取業者」「フリマアプリ」「ネットオークション」の3つの方法を、これでもかというくらい徹底的に比較してきました。
結局のところ、「絶対にこの方法が一番!」という、たった一つの正解は無いんですね。
あなたの「何を一番重視するか」によって、その答えは変わってきます。
「楽器の知識ゼロだし、梱包とか面倒なのは絶対イヤ!」「とにかく早く、安全に、ストレスなく現金化したい!」
そう思う方にとっては、「楽器買取業者」が間違いなく最適解です。
フリマで売るよりも安いかもしれないその差額は、面倒な梱包作業や、輸送破損、個人間クレームといったあらゆるリスクをゼロにしてくれるための、「安心サービス料」だと考えるのが、一番合理的だと僕は思います。
一方で、「楽器の知識なら自信がある!」「梱包作業もDIYみたいでむしろ好きだ!」「リスクは承知の上で、1円でも高く売りたい!」
そういう情熱とマメさ、そして時間的な余裕がある方なら、「フリマアプリ」や「ネットオークション」で高値を狙って挑戦する価値は、もちろん十分にあります。
どの方法を選ぶにしても、第6章でお話しした「売る前のひと手間(清掃や付属品集め)」、そして(特に業者に売る場合は)「必ず複数の業者で相見積もりを取る」というコツは、ぜひ実践してみてください。
これをやるだけで、あなたの「手残り」は確実に変わってきますからね。
一番大切なのは、「いくらで売れたか」という金額そのものよりも、「ああ、この方法で手放して良かったな」と、ご自身が心から「納得」できることだと思います。
あわせて読みたい!楽器売却の「悩み別」深掘りガイド
この記事では、楽器を売る主な3つの方法(買取業者・フリマ・オークション)を徹底的に比較し、それぞれの全体像やメリット・デメリットを解説してきました。
「だいたいの違いは分かったし、自分は業者がいいかな?いや、やっぱりフリマかな?」と、ご自身の方向性が見えてきたかと思います。
でも、中には「もっとこういう場合はどうなの?」と、さらに具体的な悩みが出てきた方もいるかもしれませんね。
ここでは、そうした「楽器売却」に関する個別の疑問について、さらに深く掘り下げた関連記事をいくつかご紹介します。
例えば、この記事を読んで「フリマアプリやオークションの手間とリスクが、やっぱり気になる…」と感じた方は、その「致命的なデメリット」について、もっと生々しく解説したこちらの記事が参考になるはずです。
→ 楽器をメルカリ・ヤフオクで売るメリットと致命的なデメリット
また、「専門業者が良いのは分かったけど、正直、近所にある地元のリサイクルショップに持ち込むのと、どれくらい査定額って違うものなの?」と迷っている方も多いと思います。
その疑問には、この記事でハッキリとお答えしています。知らないと損をするかもしれませんよ。
→ 地元のリサイクルショップに楽器を持ち込むのはアリ?専門買取との違い
「そもそも、ウチの押入れにあるこのギター、音も出ないしネックも反ってる気がする…」と、売ること自体を諦めかけている方もいるかもしれませんね。
いえいえ、ちょっと待ってください。
そんな壊れた楽器(ジャンク品)でも、値段がつく可能性は十分にあるんです。
最後に、「自分が持っているのは、かなり古いビンテージ品だ」あるいは「ギブソンやマーチンみたいなハイブランドの楽器だ」という方。
そうした特別な価値を持つ楽器を、その価値が分からない相手に売ってしまうことほど、もったいないことはありません。
その価値を最大限に引き出し、最高値で売るための方法については、こちらで詳しく解説しています。
→ ヴィンテージ楽器・ハイブランド楽器を「高く」売るための一番良い方法
これらの記事もぜひ参考にしていただき、あなたの大切な楽器が、一番納得できるかたちで手放せることを心から願っています。