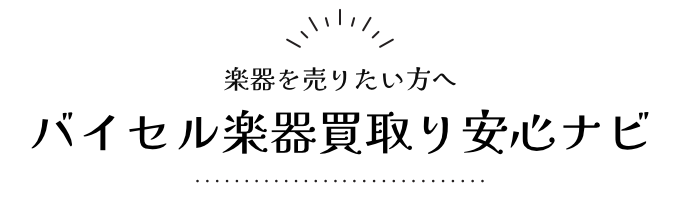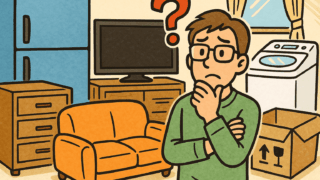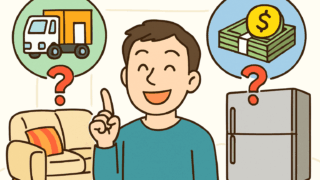使わなくなったギター、もう弾かなくなったキーボード。
部屋の隅でホコリをかぶって、正直ちょっと邪魔になっていませんか?
私も昔、バンドをやっていた頃のベースが長らく物置の主になっていた時期があって、「これ、どうしようかなぁ…」と悩んだ経験があります(笑)。
「よし、思い切って捨てよう!」
そう決意した時、まず頭に浮かぶのが「粗大ごみ」ですよね。
でも、ちょっと待ってください。
その楽器、何も考えずに「粗大ごみ」として捨ててしまうの、めちゃくちゃ「損」をしているかもしれませんよ。
「え、捨てるのにお金がかかるのは知ってるけど、それ以外に何かあるの?」
はい、あるんです。
ここでは、楽器を「捨てる」場合に、あなたが想像している以上に面倒な手続きと、意外とかかる費用(コスト)のリアルな実態を、まず徹底的に解説します。
そして、その全ての面倒ごとから解放されて、むしろ「臨時収入」までゲットできちゃうかもしれない、最高にお得な「ある方法」まで、詳しくお伝えしていきますね。
あなたのその楽器、ごみとしてお金を払って処分する前に、ぜひこの記事を5分だけ、読み進めてみてください。
知っているのと知らないのとでは、大違いですから。
楽器を「捨てる」のはもったいない?廃棄にかかる手間と費用
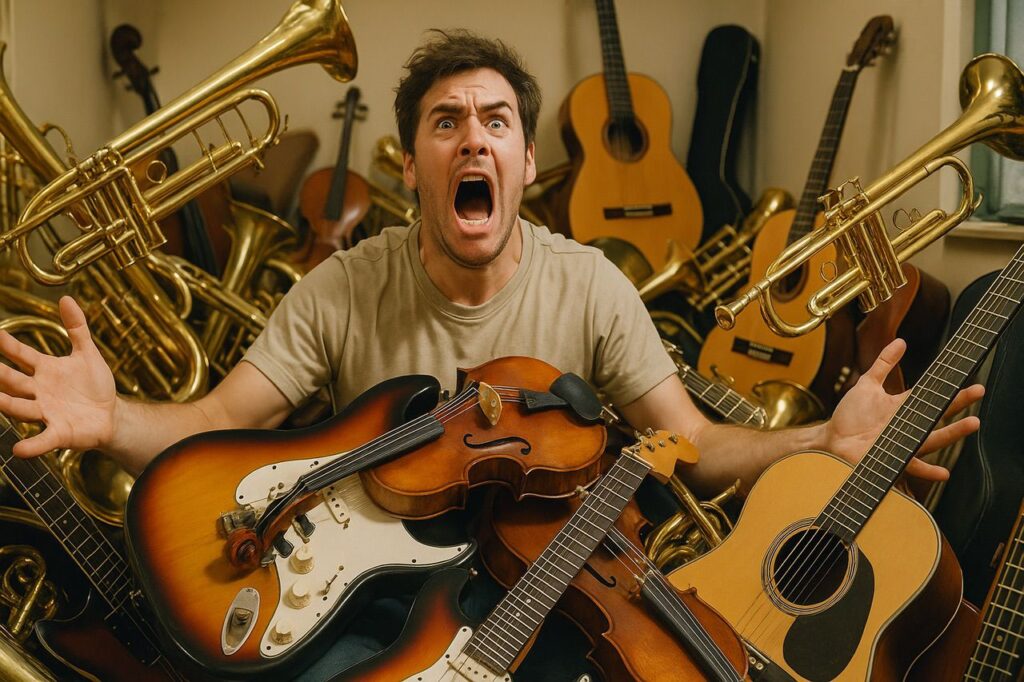
使わなくなった楽器、部屋の隅でホコリをかぶっていませんか。
「もう弾かないし、場所を取るから捨てたいな」。
うんうん、その気持ち、すごくよくわかります。
私も昔使っていたキーボードが長らく物置部屋の主になっていた時期がありましたから(笑)。
でも、ちょっと待ってください。
この記事のタイトルの通り、その楽器、「捨てる」のはかなり損かもしれません。
なぜなら、楽器を「廃棄」するのって、思った以上に「費用」と「手間」がかかるんですよ。
ここでは、まず「楽器を捨てる」という選択をした場合、具体的にどんな手順とコスト、そしてデメリットがあるのかを詳しく見ていきます。
本当にその方法でいいのか、一緒に考えていきましょう。
そもそも楽器は「ごみ」として捨てられる?
はい、結論から言うと、ほとんどの楽器は「ごみ」として捨てることが可能です。
ただし、残念ながら(?)普段の「燃えるごみ」や「不燃ごみ」の袋に入れてポイッと出すことはできません。
まあ、そりゃそうですよね、あんなに大きいですし。
ほとんどの自治体では、楽器は「粗大ごみ」として扱われることになります。
この「粗大ごみ」の定義が、また厄介なんです。
例えば、「一番長い辺が30cm以上のもの」とか「50cm以上のもの」とか、お住まいの自治体によってルールが全然違います。
小さい管楽器(トランペットとか)なら不燃ごみでOKな場所もあれば、ギターケースだけでも粗大ごみ扱いになる場所もあるようです。
なので、まずは「自分(あなた)が住んでいる市区町村のルール」を調べることが、廃棄への第一歩になりますね。
この時点で、すでにちょっと面倒な感じがします…。
楽器の廃棄(処分)にかかる費用の目安
「粗大ごみで出せるんだ、よかった」と思ったかもしれませんが、残念ながら多くの場合、無料ではありません。
粗大ごみを捨てるには、「粗大ごみ処理手数料」というコストがかかります。
これも自治体によって料金はピンキリなんですが、一般的な目安としてはこんな感じでしょうか。
・ギター、ベース、キーボード(小さいもの):400円~1,000円程度
・電子ピアノ、エレクトーン(運べるサイズのもの):1,000円~2,500円程度
・アンプやスピーカー:400円~1,200円程度
どうでしょう。
「え、捨てるのにお金払うの?」って、ちょっと思っちゃいますよね。
もちろん、これはあくまで一例です。
もっと安い地域もあれば、もっと高い地域もあります。
いずれにしても、弾かなくなった楽器を処分するために、わざわざ数百円から数千円を支払う必要がある、というのは覚えておかないといけないですね。
うーん、やっぱりもったいない感じがします。
廃棄処分はこんなに面倒!手続きの手間と時間
お金(費用)だけじゃありません。
「手間」も相当かかるのが、粗大ごみ処分のリアルです。
一般的な粗大ごみの手順は、だいたいこんな流れです。
1. 自治体の「粗大ごみ受付センター」に電話やインターネットで事前申し込み。
2. 処分したい楽器の品目(ギターとか)を伝えて、手数料と収集日、収集場所を確認。
3. コンビニや郵便局などで、指定された金額の「処理手数料券(シール)」を購入。
4. シールに名前や受付番号を書いて、楽器に貼り付ける。
5. 指定された収集日の朝(だいたい朝8時とか)、指定された場所(家の前やごみ集積所)まで、自分で運び出す。
…これ、どう思います?
私、正直に言って、かなり面倒くさいっす(笑)。
特に最後の「自分で運び出す」がクセモノです。
ギター1本ならまだしも、大型のキーボードやアンプ、ドラムセットの一部なんて、一人で運ぶのは重労働ですよね。
しかも収集日の朝って、忙しい時間帯じゃないですか。
これをやるくらいなら、まだ部屋に置いておくか…と先延ばしにしてしまう人の気持ち、よーくわかります。
まだ使える楽器を捨てる罪悪感…環境への影響は?
費用と手間、これが実利的なデメリットです。
でも、もう一つ、見過ごせないデメリットがあります。
それは「罪悪感」です。
昔は夢中になって練習したギター、必死にバイトして買ったベース、子供が使っていたピアノ…。
それを「ごみ」として処分するのって、なんだか心が痛みませんか。
「もったいないな」「なんか、バチが当たりそう…」みたいな感覚、誰にでもあると思うんです。
まだ音が出るのに、まだ誰かが使えるかもしれないのに、自分の手で「ごみ」のシールを貼るわけですからね。
それに、環境への影響も気になるところです。
粗大ごみとして出されたものが、すべてリサイクル(資源として再利用)されるとは限らないようです。
自治体によっては、そのまま破砕されて埋め立てられるケースも多いと聞きます。
大切にしていた楽器が、ただの「埋め立てごみ」になってしまうのは、ちょっと悲しいですよね。
楽器にとっても、地球にとっても、ベストな選択とは言えないかもしれません。
【体験談】粗大ごみで楽器を捨てようとした人のリアルな声
ここまで「費用」「手間」「罪悪感」というデメリットを見てきました。
「大げさな」と思うかもしれませんが、実際に楽器を粗大ごみで捨てようとして、挫折した人や後悔した人の声って、結構多いんですよ。
ネットやSNSなんかでよく見かける「あるある」な声をちょっと集めてみました。
「粗大ごみセンターに電話したけど、年度末の引っ越しシーズンで全然つながらない!」
「ネットで申し込んだけど、収集日が2週間も先。それまで部屋にあって邪魔…」
「手数料シール買いに行くの忘れてて、収集日当日の朝に気づいた(笑)」
「キーボードが重すぎて、アパートの階段から降ろせなかった。結局諦めた」
「当日雨が降ってて、楽器を濡らして出すのが忍びなくてやめた」
どうです?
「あー、やりそう…」って思った方もいるんじゃないでしょうか。
はい、まさにこれがリアルな声です。
楽器の廃棄って、決意してから完了するまで、意外とハードルが多いんですよね。
ただ捨てるだけなのに、こんなに面倒なら、やっぱり「捨てる」のは損な選択肢だと思いませんか。
【自治体別】楽器を粗大ごみで捨てる手順と料金相場

さて、前のセクションでは「捨てるのは損かも」という話をしましたが、「いや、それでも自分は捨てる!」と決意が固い方もいらっしゃいますよね。
もちろん、それも一つの選択です。
ここでは、楽器を「粗大ごみ」として捨てる場合の、具体的な手順や費用の相場について解説していきます。
ただし、ここで一番、本当に一番大事なことを先にお伝えします。
それは、「ルールは自治体(市区町村)によって全く違う」ということです。
ここで紹介するのは、あくまで「一般的な流れ」の一例です。
最終的には、必ずあなたがお住まいの自治体の公式情報を確認してくださいね。
約束ですよ(笑)。
ステップ1:お住まいの自治体のルールを確認
まず、何はともあれ、これです。
「(お住まいの市区町村名) 粗大ごみ 楽器」とか「(お住まいの市区町村名) 粗大ごみ ギター」みたいに検索すれば、すぐに自治体の公式ホームページが見つかるはずです。
そこで確認すべきことは、大きく分けて3つ。
1. 品目:その楽器が「粗大ごみ」の対象か?(違う場合は捨て方(例:不燃ごみ)も書いてあるはずです)
2. 料金:捨てるのに、いくらかかるのか?(手数料)
3. 方法:どうやって捨てるのか?(家まで収集に来てくれるのか、自分で持ち込むのか)
この3点をしっかり確認するのが、廃棄へのスタートラインですね。
電話で問い合わせる窓口もありますが、まずはネットで確認するのが早いかな、と個人的には思います。
自治体のホームページって、ちょっと情報が探しにくいこともありますが…頑張って見つけましょう。
ステップ2:粗大ごみ受付センターへの申し込み方法
捨てる楽器の料金やルールがわかったら、次に「申し込み」をします。
勝手に捨てちゃダメですよ、もちろん。
申し込み方法は、だいたい「電話」か「インターネット」のどちらか(または両方)が用意されています。
電話は「粗大ごみ受付センター」みたいな専門の窓口があることが多いですね。
ただこれ、引っ越しシーズン(3~4月)や、週明けの月曜日の午前中なんかは、もう「まじで繋がらない」ってことがよくあります(笑)。
私も昔、別の用事で電話した時、20分くらい保留音を聞き続けた記憶が…トホホ。
なので、個人的には24時間いつでも申し込める「インターネット受付」が便利かな、と思います。
申し込みの際には、収集日、収集場所(家の前とか)、手数料の金額を伝えられるので、忘れないように必ずメモしておきましょう。
ステップ3:手数料(シール・券)の購入と貼り付け
申し込みが済んだら、次はお金(手数料)の支払いです。
当日に収集スタッフさんに現金で払う…わけじゃないんですよね、これが。
ほとんどの自治体では、「粗大ごみ処理手数料券」とか「ごみ処理券」「シール」と呼ばれるものを、事前に購入するシステムになっています。
どこで買えるかというと、これも自治体によって指定されています。
だいたいは「市内のコンビニエンスストア」「郵便局」「スーパーマーケット」などで取り扱っていることが多いようです。
申し込み時に案内された金額(例えば「ギター400円」なら400円券を1枚)分を購入します。
これも「あるある」なんですが、収集日ギリギリになって「あ、シール買ってない!」って焦るパターン。
申し込みしたら、早めに買っておくのが吉ですね。
買ってきたシールには、受付番号や氏名、収集日などを記入して、処分する楽器の目立つところにペタッと貼り付けます。
これで準備OKです。
ステップ4:指定の日時・場所への搬出
さあ、いよいよ最後のステップ、これが一番の難関かもしれません。
「搬出」です。
申し込み時に指定された「収集日の朝(例:朝8時まで、とか8時30分まで、とか)」に、指定された「場所(例:自宅の玄関前、アパートの1階の共用玄関、指定のごみ集積所など)」まで、自分で楽器を運ばないといけません。
そう、「自分で」運ぶんです。
収集スタッフさんが部屋の中まで取りに来てくれるわけじゃありません(※一部、高齢者向けサービスなどを除く)。
収集日の前日の夜から出しておくと、盗難や放火のリスクがあるからダメ、というルールの自治体も多いようです。
朝の忙しい時間に、重いキーボードやアンプを階段で降ろして運ぶ…想像しただけで、ちょっと腰が痛くなりそうですよね(笑)。
もちろん、その日が雨でも雪でも、基本的には決行です。
楽器が濡れちゃう…なんて感傷に浸るヒマもなく、置いてこないといけないわけです。
これが、粗大ごみのリアルな「手間」ですね。
主要都市(東京・大阪・名古屋など)の粗大ごみ費用比較
「自治体によってルールが違う」と何度も言いましたが、じゃあ「費用」はどれくらい違うんでしょうか。
参考までに、いくつかの主要都市の例を(執筆時点で調べた一例として)挙げてみますね。
【ギター(アコースティックギターなど)の場合】
・東京都 新宿区:400円
・大阪府 大阪市:200円
・愛知県 名古屋市:250円
【キーボード(電子ピアノ除く、61鍵盤程度のもの)の場合】
・東京都 新宿区:800円
・大阪府 大阪市:400円
・愛知県 名古屋市:500円
※あくまで一例です。必ず最新の情報を各自治体でご確認ください!
どうですか?
同じ楽器でも、大阪市と新宿区では倍くらい違うんですね!
これは驚きです。
キーボード1台捨てるのに800円か…と思うと、やっぱりちょっと「うーん」と考えちゃいますよね。
繰り返しになりますが、これはあくまで一例。
あなたの街がいくらなのかは、必ずご自身で確認してくださいね。
自分で持ち込む「持ち込み処分」は得?
粗大ごみの捨て方、実はもう一つあります。
それは、収集車に来てもらうのではなく、「自分で直接、ごみ処理施設(クリーンセンターとか)に持ち込む」方法です。
多くの自治体で、この「持ち込み処分」が認められています。
メリットは、なんといっても手数料が安くなるケースが多いこと。
自治体によっては「収集の半額」になったり、「重量制(10kgあたり〇〇円)」で計算したら結果的に安くなったりするようです。
あとは、収集日を待たずに、施設の受付時間内なら(予約は必要な場合も)、自分のタイミングで捨てに行けるのもメリットかもしれません。
ただ、もちろんデメリットもあります。
当然ですが、施設まで運ぶ「車」が必須です。
そして、その施設がだいたい郊外の、ちょっと遠い場所にあったりします。
重い楽器を車に積んで、運転して、施設でまた自分で降ろして…という手間をどう考えるか、ですね。
車を持っていて、運ぶ力もあって、少しでも費用を浮かせたい!という人には、アリな選択肢かもしれません。
要注意!粗大ごみで出せない楽器(ピアノなど)と、条件付きの楽器(エレクトーン)

さて、ここまで「楽器は粗大ごみ」という前提でお話を進めてきました。
ですが、ここに大きな、本当に大きな例外があります。
そう、ご想像の通り「ピアノ」や「エレクトーン」といった大型の鍵盤楽器です。
これらは、そもそも粗大ごみとして収集してもらえなかったり、収集してもらえるとしても、かなり厳しい条件が付いたりすることがほとんどなんです。
「うちのキーボード、ちょっと大きいけど大丈夫かな?」とか「エレクトーンなんだけど…」という方。
ここを読み飛ばしてしまうと、いざ申し込んだ時に「あ、それ、うちは収集できません」と断られてしまう悲劇が待っているかもしれません。
ここはよーく確認していきましょう。
なぜピアノは粗大ごみNGが基本なの?
まずは、ピアノ(アップライトピアノ、グランドピアノ)です。
はい、結論から申し上げますと、これらは「ほぼ100%、自治体の粗大ごみでは捨てられません」。
理由は、もう、シンプルですよね。
「重すぎ・デカすぎ」問題です(笑)。
自治体の粗大ごみ収集というのは、基本的に「収集作業員の方が2名、もしくは3名程度で運べるもの」を前提としています。
アップライトピアノでも平均200kg以上、グランドピアノなんてもっとです。
これを、朝のごみ収集で「よっこいしょ」と持っていくのは、どう考えても無理がありますよね。
こうした規格外のものは、自治体によっては「適正処理困難物」なんていう、ちょっと難しい名前で呼ばれていて、「ごめん、うち(自治体)じゃ扱えないんです」というリストに入っていることがほとんどです。
なので、ピアノの処分は、粗大ごみに申し込む、という発想自体をまずリセットする必要があります。
エレクトーンは「粗大ごみ」?自治体別の重量制限と注意点
では、エレクトーン(電子オルガン)はどうでしょう。
これがちょっとややこしいんです。
お住まいの自治体の粗大ごみ品目リストを見てみると、「エレクトーン」とか「電子オルガン」という項目が、ちゃんと載っている場合があります。
「お!エレクトーンは粗大ごみでOKなんだ!よかった!」
…と、喜ぶのはまだ早いかもしれません。
ここに、自治体ごと、そしてエレクトーンごとの「落とし穴」があります。
それは、品目リストの注釈や、粗大ごみのルール詳細に書かれている「重量制限」や「サイズ制限」です。
例えば、「大人2名で運搬できるものに限る」とか、「重さが70kg(または100kg)を超えるものは収集できません」といった一文が、こっそり(?)書かれていることが多いんです。
最近のコンパクトなモデルならクリアできるかもしれませんが、問題は処分したいと思うような「古いモデル」です。
昔のエレクトーンって、すごく立派な作りで、平気で100kgを超えている機種がたくさんあります。
そうなると、リストには載ってるけど、うちのエレクトーンは重量オーバーで「収集不可」。
これ、結構“あるある”な罠ですよね…。
なので、まずは処分したいエレクトーンの型番を調べて、重さを確認すること。
そして、自治体のルールで重量制限がないか、をセットで確認することが必須ですね。
ピアノ・エレクトーン専門の処分業者の費用相場と流れ
では、粗大ごみとして捨てられないと判明したピアノや、重量オーバーのエレクトーンは、どうすればいいんでしょうか。
はい、これはもう「専門の業者」に依頼する、というのが答えになります。
「ピアノ専門の運送業者さん」や、「楽器の処分を専門に扱っている不用品回収業者さん」ですね。
流れとしては、だいたいこんな感じです。
1. 業者さんに電話やネットで見積もりを依頼します。
(伝えること:楽器の種類、メーカー・型番、設置場所(戸建てかマンションか、何階か、エレベーターはあるか、など))
2. 見積もり金額(処分費用)が提示されます。
3. 金額に納得したら、引き取りに来てほしい日時を予約します。
4. 当日、専門のスタッフさん(屈強な方々)がやってきて、養生(床や壁の保護)をした上で、手際よく運び出してくれる。
費用は、粗大ごみとは比較になりません。
数万円(1万円台~5万円以上)はかかるのが一般的です。
特にピアノで、階段から降ろしたり、クレーンを使ったりする必要があると、費用はさらに上がります。
「うわ、高い…」と思うかもしれませんが、あの重くてデリケートなものを、家を傷つけずに安全に運び出してもらうための「技術料」「人件費」ですね。
さすがにこれはプロの仕事だな、と割り切るしかなさそうです。
防音室や大型アンプなど周辺機材の処分
楽器本体だけでなく、周辺機材の処分に困るケースもありますよね。
特に「防音室(組み立て式のユニットタイプ)」や、バンドマンが使うような「大型のアンプ(マーシャルのスタックアンプとか)」「PA用のミキサー卓」あたり。
これ、どう捨てればいいか、本当に迷うと思います。
まず、防音室。
これはピアノと同じく、まず間違いなく「専門業者の解体・撤去」が必要です。
粗大ごみでは絶対に無理ですね。
大型のアンプやミキサー卓は、エレクトーンとちょっと似た立ち位置です。
自治体によっては「アンプ」として粗大ごみの品目にあっても、やっぱり「重量制限」や「サイズ制限」に引っかかる可能性があります。
「一人で持てないサイズのアンプ」は、粗大ごみは無理かも、と疑ったほうがいいかもしれません。
このあたりも、まとめて専門業者さんに見積もりを取ってしまうのが、一番手っ取り早くて確実な気はしますね。
リサイクル法(家電リサイクル法など)との関連は?
たまに誤解される方がいるんですが、「楽器って、家電リサイクル法の対象なの?」という疑問。
テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンを捨てる時って、「家電リサイクル券」を買って、決められた料金を支払う必要がありますよね。
結論から言うと、「(現在のところ)楽器は、家電リサイクル法の対象外」です。
なので、あのリサイクル券を楽器のために買う必要は、基本的にはありません。
ただし、ちょっとややこしいのが、「スピーカー」や「アンプ」単体の場合。
これらは自治体によっては「小型家電リサイクル法」という別の法律の対象として、「回収ボックスに入れてね」とか「(大きいものは)粗大ごみで」と案内されるケースがあるようです。
とはいえ、家電リサイクル法とは別物です。
基本的には、楽器(電子ピアノやキーボード、ギターアンプなども含む)は「粗大ごみ」か「(ピアノなどの)専門業者による処分」、このどっちか。
そう覚えておけば、大きく間違うことはないと思いますよ。
ギター、ベース、キーボード…種類別の捨て方まとめ

さて、ここからは、より具体的に「私の持ってるコレ、どうなの?」という疑問にお答えしていきます。
ピアノやエレクトーンほどではないけれど、処分に迷いがちな主要な楽器たち。
ギター、ベース、キーボード、ドラムなど、種類別の捨て方のポイントをまとめてみました。
前のセクションまでで「粗大ごみ」が基本、と解説してきましたが、楽器によってちょっとずつ注意点が違ったりするんですよね。
ご自身の持っている楽器の項目を、ぜひチェックしてみてください。
(※もう耳にタコかもしれませんが、最終的なルールは、あなたのお住まいの自治体のホームページなどで必ず確認してくださいね!)
アコースティックギター・クラシックギターの捨て方
まずは楽器の定番、アコースティックギター(アコギ)やクラシックギターです。
これらは、多くの自治体で「粗大ごみ」として扱われています。
おそらく、一番わかりやすいパターンじゃないでしょうか。
自治体の粗大ごみ品目リストにも「ギター」として、400円とか500円とか、料金が明記されていることが多いです。
申し込む時も「アコースティックギターです」とそのまま伝えればOK。
比較的、悩むことは少ない楽器だと思います。
ただ、ちょっと注意したいのが「ケース」の扱いです。
ペラペラのソフトケースなら、一緒に袋に入れて捨てられる(または燃えるごみ?)かもしれません。
でも、頑丈な「ハードケース」は別。
ハードケース自体が、それ単品で「粗大ごみ」として扱われる(別途料金がかかる)可能性が結構高いんです。
「ケースも一緒に捨てたいんですけど、料金は変わりますか?」と、申し込みの時にひと言確認してみるのが確実ですね。
エレキギター・ベースの捨て方(アンプはどうする?)
続いて、エレキギターやエレキベース。
これらも、楽器本体の扱いはアコギとほぼ同じです。
「粗大ごみ」として申し込むのが基本ですね。
長さがありますから、不燃ごみで…というのは、ちょっと難しいでしょう。
もちろん、これもハードケースの扱いは要確認ですよ。
そして、エレキ楽器に付き物なのが「アンプ(ギターアンプ、ベースアンプ)」です。
これがまた、サイズによって扱いが変わるからややこしい。
自宅練習用の、本当に小さなミニアンプ(一辺が15cmとか20cmとか)なら、「不燃ごみ」や「小型家電リサイクル」の回収ボックスでOK、という自治体も多いようです。
ですが、ちょっと本格的な練習用アンプ、いわゆる「コンボアンプ」(一辺が30cmを超えるようなもの)になると、もうこれは立派な「粗大ごみ」です。
ギター本体とは別に、「アンプ 1点 〇〇円」という申し込みが必要になります。
もちろん、料金もそれぞれにかかってきます。
「ギターとアンプ、セットでいくら」みたいにはならないのが、ちょっと世知辛い感じもしますよね(笑)。
自治体によっては「不燃ごみ」?ケースバイケースの判断基準
「ギター 捨て方」で調べると、たまに「不燃ごみで捨てられた」という体験談を見かけることがあります。
これは、どういうことなんでしょうか。
はい、これはもう「その自治体のルールがそうだったから」としか言えないんですよね。
例えば、ある市のルールが「一番長い辺が50cm未満のものは不燃ごみ」だとします。
ギターのネックを外して、ボディとネックを別々にすれば…確かに50cm未満になるかもしれません。
でも、正直なところ、そこまでして解体する手間、すごくないですか?
ドライバーやレンチで分解して、弦も切って…。
そこまで頑張るくらいなら、素直に400円とかの手数料を払って「粗大ごみ」で出す方が、よっぽど楽じゃないかな?と、私なんかは思ってしまいます。
それに、自治体によっては「解体しても、元の形が粗大ごみサイズなら、粗大ごみとして申し込んでください」という、通称「解体しても無駄ルール」(私が勝手に呼んでます)を採用しているところも多いんです。
変に頑張って、収集されなかったら目も当てられませんからね。
ミニギターとか、トラベルギターみたいな小さいものなら、不燃ごみでいける可能性もゼロではないかもしれませんが…やはり、まずは確認。
「ギターは粗大ごみ」、そう思っておくのが一番安全な気がします。
アンプやエフェクターなど周辺機器の処分ルール
アンプのルールについても、もう少しだけ詳しく見てみましょう。
「小さいのは不燃ごみ、大きいのは粗大ごみ」と言いました。
では、ライブハウスやスタジオにあるような、アンプの頭(ヘッド)と、スピーカーの箱(キャビネット)が分かれている「スタックアンプ」はどうでしょう。
はい、これはもう、粗大ごみどころか、前のセクションで出てきた「専門業者」案件になる可能性が高いです。
特にスピーカーが4発入ってる大型キャビネット(通称ヨンパツ)なんて、とんでもなく重くて大きいですから。
これはもう、ピアノやエレクトーンと同じカテゴリーで、「自治体では収集困難」と言われる可能性が非常に高いですね。
「マーシャルのスタックなんですけど…」と、寸法と(わかるなら)重さを伝えて、収集可能か自治体に直接問い合わせる必要があります。
あと、忘れがちなのが足元に並べる「エフェクター」たち。
BOSSのコンパクトエフェクターみたいな、あの小さな金属の箱ですね。
これらは、サイズ的にも「不燃ごみ」や「小さな金属類」として捨てられることがほとんどです。
ただ、捨てる前に必ず「電池(9V電池とか)」は抜いてくださいね。
電池が入ったまま捨てると、発火などの原因になることがあるようです。
こういう細かい周辺機器も、ルールを守って正しく処分したいものですね。
キーボード・シンセサイザーの捨て方
これも処分に迷う楽器の代表格ですね、キーボード。
一口に「キーボード」と言っても、サイズが本当にピンキリです。
子供の頃に使っていたような、電池で動く小さなポータブルキーボード(カシオトーンとかピアニカとか)。
これくらいなら、自治体によっては「不燃ごみ」(または、乾電池を使うから「有害ごみ」?)、サイズが大きければ「粗大ごみ」になるでしょう。
問題は、もっと本格的な、61鍵盤、76鍵盤、88鍵盤といった「シンセサイザー」や「デジタルピアノ(スタンド一体型じゃない、ステージピアノみたいなやつ)」です。
これはもう、前のセクションでお話しした「エレクトーン」と、ほぼ同じ考え方になります。
そう、自治体の粗大ごみリストに「キーボード 800円」とか載っていたとしても、安心するのは早い、ということです。
チェックすべきは「重量制限」と「サイズ制限」。
特に88鍵盤の、ピアノタッチを再現した「ウェイテッド鍵盤」のモデルは、見た目に反してめちゃくちゃ重いんですよね。
平気で20kgとか超えてきます。
「重さが〇〇kgを超えるものは収集できません」という注釈がないか、よーく確認してください。
重いシンセサイザーを、無理して朝イチで運んで腰を痛めたら、処分手数料(800円)より、よっぽど高い治療費がかかっちゃいますからね(笑)。
無理は禁物です。
ドラムセットの部分的な処分方法(シンバル・スタンドなど)
ドラマーの方、お待たせしました。ドラムセットです。
これも、想像するだけで処分が大変な楽器のトップクラスですね。
もちろん、あのセットのまま「ドン!」と捨てることはできません。
バスドラム(一番大きいの)、スネアドラム(真ん中の)、タムタム、フロアタム、シンバル、ハイハットスタンド、シンバルスタンド、スローン(椅子)…と、全部バラバラにして、パーツごとに処分することになります。
そして、悲しいお知らせですが、そのパーツの「ほぼすべて」が、それぞれ「粗大ごみ」扱いになると思った方がいいです。
「バスドラム 1点 〇〇円」「タム 1点 〇〇円」「スタンド 1点 〇〇円」…という具合に、それぞれに手数料がかかります。
フルセット捨てようと思ったら、申し込む品目も10点近くなるかもしれませんし、費用も全部合計すると、かなりの金額になりそうです。
「ドラムセット一式でいくら」とは、まずならないのが辛いところですよね。
唯一、シンバル(ハイハットやクラッシュ、ライド)そのもの。
あれは金属の円盤なので、「不燃ごみ」や「資源ごみ(金属類)」として出せる自治体も多いようです。
でも、それを立てるスタンド類(金属の棒)は、長さがありますから、まず粗大ごみでしょうね。
ドラムセットの処分は、ある意味ピアノの次に大変かもしれません。
パーツごとに分別して、申し込んで、運び出して…考えただけで、ちょっと気が遠くなります…。
管楽器(トランペット・サックスなど)や弦楽器(バイオリンなど)の場合
最後に、比較的コンパクトな楽器たち。
トランペット、トロンボーン、サックス、フルート、クラリネットなどの管楽器。
そして、バイオリン、ビオラ、チェロなどの弦楽器(※コントラバスはデカいので別枠かも)。
これらはどうでしょう。
楽器本体だけを見れば、そんなに大きくないですよね。
自治体が定める「一番長い辺が30cm(または50cm)未満なら不燃ごみ」というルールに収まるものも多いはずです。
そう、これらは「不燃ごみ」として捨てられるケースが結構あるようです。
「なーんだ、簡単じゃん」と思いましたか?
でも、ここにもちょっとした罠があります。
それは、やっぱり「ハードケース」です。
特にサックス(アルトやテナー)のハードケース、そしてチェロのハードケース。
これ、本体は収まっていても、ケース自体がもう立派な「粗大ごみ」サイズじゃないですか?
なんだか皮肉な感じもしますよね。
楽器本体は「不燃ごみ」なのに、それを大切に守ってきたケースの方が「捨てるのが面倒な粗大ごみ」だなんて。
この場合、自治体に「ケースごとまとめて粗大ごみでいい?」と確認してみるのが手っ取り早いかもしれません。
もし「本体は不燃ごみ、ケースは粗大ごみで」と案内されたら、ちょっと手間ですが、分別して捨てることになりますね。
チェロは本体も粗大ごみサイズかもしれません。
やはり、最後まで「自治体ルール確認」からは逃れられないようです。
「捨てる」以外の選択肢!楽器は“売る”方が断然お得な理由

さて、ここまでのセクションで、「楽器を捨てる」というのが、いかに「費用」と「手間」がかかる面倒な作業か、これでもかというほど解説してきました。
「うわー、捨てるのってこんなに大変なのか…」
「お金もかかるし、朝から運ぶとか無理かも…」
と、ちょっとウンザリしている方も多いんじゃないでしょうか。
はい、まさにそれこそが「捨てる」ことのリアルです。
でも、待ってください。
もし、その「かかる費用」がゼロになり、「面倒な手間」も一切なくなり、さらには「捨てる罪悪感」まで解消される、そんな方法があるとしたら…知りたくありませんか?
その、まさに「捨てる」とは真逆の、お得な選択肢。
それが、「楽器買取りサービスを利用する」=「売る」という方法なんです。
なぜ、楽器の処分は「捨てる」より「売る」方が断然お得なのか。
その明確な理由を、一つずつ見ていきましょう。
理由1:廃棄費用(数千円)がゼロになる
まず、一番わかりやすいメリットがこれです。
「廃棄費用」が、まるっと「ゼロ円」になります。
粗大ごみで捨てる場合、必ずかかってしまう「粗大ごみ処理手数料」。
ギター1本でも数百円、キーボードやアンプなら1,000円前後、自治体で無理なピアノやエレクトーンを専門業者に頼んだら、数万円の「処分費用」がかかる…というお話をしましたよね。
これ、冷静に考えるとおかしくないですか?
いらないモノを処分するために、なぜか自分がお金を払わないといけないんです。
でも、「買取サービス」を利用すれば、この手数料や処分費用は一切かかりません。
当たり前ですよね、だって「売る」んですから。
「お金を払って捨てる」というマイナスのアクションが、まず「ゼロ」になる。
これだけでも、あの面倒な手数料シールを買いに行ったり、いくらかかるかビクビクしたりする必要がなくなるわけで。
めちゃくちゃ大きなメリットだと思いませんか。
理由2:逆にお金がもらえる(臨時収入になる)
はい、ゼロになるだけじゃありません。
ここが「売る」ことの最大の魅力です。
「逆にお金がもらえちゃう」んです。
「え、まじで?」って感じですよね(笑)。
そうです、あなたが「場所ふさぎだ」「もういらない」と、お金を払ってでも捨てようとしていたその楽器が、お金に化ける可能性があるんです。
もちろん、どんな楽器でも高額になるわけではありません。
でも、数百円、数千円、あるいは人気のモデルや状態が良ければ、数万円になることだって全然珍しくありません。
処分にお金(マイナス)がかかるどころか、逆にお金(プラス)が自分の懐に入ってくる。
まさに「捨てるのは損!」というタイトルの意味が、これでお分かりいただけるかと思います。
そのお金で、新しい機材の足しにしてもいいですし、ちょっと美味しいランチやディナーに行くことだってできますよね。
臨時収入、万歳!って感じです。
理由3:面倒な搬出や手続きをすべてお任せできる
お金のメリットはわかった。
でも、どうせ「売る」のも面倒なんでしょ?
そう思うかもしれません。
いえいえ、そこが「捨てる」場合との決定的な違いです。
粗大ごみの、あの面倒な手続きをもう一度思い出してください。
1. 自治体に電話(なかなかつながらない)かネットで予約。
2. コンビニで手数料シールを買う。
3. 楽器にシールを貼る。
4. 指定された日の朝(早い)、指定された場所(家の外)まで、自力で運び出す。
…思い出しただけで、ため息が出ますよね(笑)。
特に最後の「自力で搬出」、重いキーボードやアンプだったら、本当に苦行です。
ですが、楽器の買取サービス、特に「出張買取」や「宅配買取」を選べば、これらの手間は、驚くほど「ゼロ」になります。
「出張買取」なら、予約した日時に、専門スタッフさんが家まで来てくれて、査定から運び出しまでぜーんぶやってくれます。
こっちは、文字通り「見てるだけ」(笑)。
重い楽器を階段で降ろす必要もありません。
「宅配買取」なら、送られてくる梱包材(ダンボールとか)に楽器を詰めて、配送業者さんに集荷に来てもらうだけ。
もちろん、送料や手数料も無料のところがほとんどです。
家から一歩も出ずに、あの邪魔だった楽器が片付いて、しかもお金が振り込まれる。
これ、最強じゃないですか?
理由4: 大切にしていた楽器が次の誰かに使ってもらえる
そして、お金や手間といった実利的なメリットの他に、もう一つ、すごく大事な理由があります。
それは「気持ち」の面でのメリットです。
「捨てる」場合に、どうしても感じてしまう、あの「罪悪感」や「もったいない」という後ろめたさ。
昔はあんなに夢中になって弾いていたのに、「ごみ」として処分してしまうのは、なんだか心が痛みますよね。
その楽器が、そのまま埋め立てられてしまうかもしれない、と思うと、なおさらです。
でも、「売る」という選択なら、その罪悪感は一切ありません。
買い取られた楽器は、専門のスタッフさんによってキレイにクリーニングされ、必要なら修理・調整(メンテナンス)されます。
そして、また「楽器」として、それを必要としている新しい持ち主さんの手に渡っていくんです。
あなたが「もう弾かない」と思ったその楽器を、どこかの誰かが「これから始めたい」と探しているかもしれません。
「ごみ」になるんじゃなくて、「楽器」として、次のステージでまた新しい音を奏でることになる。
これって、すごく素敵なことだと思いませんか。
楽器にとっても、その方が絶対に幸せですよね。
捨てる罪悪感どころか、むしろ「良いことしたな」という、清々しい満足感が得られる。
これも、「売る」ことの大きな価値だと、私は思います。
古い楽器や壊れた楽器でも買い取ってもらえる?
ここまで良いことばかりをお伝えすると、きっとこう思うはずです。
「いやいや、ウチの楽器、何十年も前に親が買った、どこのメーカーかも分からない古いヤツだし」
「アンプにつないでも音が出ない、壊れたギターだし」
「鍵盤がいくつか戻ってこないキーボードだし、こんなの売れるわけないよ」
…そう思って、最初から「捨てる」一択で考えてしまう人、本当に、本当にもったいないです!
ちょっと待ってください。
楽器の買取というのは、近所のリサイクルショップで洋服や家具を売るのとは、ワケが違います。
「楽器専門」の買取業者さんには、楽器のプロフェッショナルがいます。
その「何十年も前の古い楽器」が、実は今や希少価値のある「ヴィンテージ」として、高値がつくかもしれません。
「音が出ない壊れたギター」でも、専門の技術者(リペアマン)が修理すれば、問題なく再販できるかもしれません。
あるいは、修理が無理でも、「部品取り(パーツ)」として価値がある場合だって、普通にあるんです。
「どうせ売れない」と、あなたが勝手に判断して粗大ごみに出してしまったものが、実は1万円の価値があった…なんて話、笑えないですよね。
査定だけなら「無料」のところがほとんどなんですから、「こんな状態なんですけど、値段つきますか?」と、ダメ元で聞いてみるだけ、聞いてみないと損ですよ。
その「ダメ元」が、予想外の臨時収入に化ける。それが楽器買取の面白いところなんです。
おすすめの楽器買取サービスと賢い選び方

さて、前のセクションで「捨てる」より「売る」方が、いかに魅力的かをお伝えしてきました。
「よし、じゃあ売ってみようかな」と思ったあなた。
次にぶつかる壁が「じゃあ、一体『どこ』に売ればいいの?」という問題ですよね。
そうなんです、ここも大事なポイント。
せっかく「売る」と決めたのに、変な業者に安ーく買い叩かれてしまったら、それこそ「捨てた方がマシだった(いや、それはないか)」なんて後悔をしかねません。
ここでは、楽器買取サービスの種類から、失敗しない優良な業者の選び方、そして具体的なおすすめサービスまで、しっかり解説していきます。
ここを読めば、あなたはもう「買取カモ」にはなりませんよ(笑)。
楽器買取サービスの種類(出張・宅配・持ち込み)
まず、楽器の買取方法には、大きく分けて3つの種類があります。
「出張買取」「宅配買取」「持ち込み買取」の3つですね。
これは、あなたの持っている楽器の種類や、あなたのライフスタイルに合わせて選ぶのが一番です。
・出張買取
これは、買取業者のスタッフさんが、直接あなたの家まで来てくれる方法です。
その場で楽器を査定して、金額に納得すれば、その場で運び出しておしまい(お金は後日振込か、その場払いかは業者によります)。
メリットは、なんといっても「圧倒的にラク」なこと。
こっちは何もしなくていいんですから(笑)。
ピアノ、エレクトーン、ドラムセット、大型アンプなど、「自分で運ぶのが無理」な楽器は、実質これ一択ですね。
あるいは、「ギターが10本あって、いちいち梱包するのが面倒」みたいな人にも最適です。
デメリットは、家で他人と会う必要がある、というくらいでしょうか。
・宅配買取
これは、ギター、ベース、エフェクター、管楽器など、ダンボールに梱包して送れる楽器に向いています。
業者に申し込むと、「無料の梱包キット(ダンボールや緩衝材)」を送ってくれることが多いです。
それに楽器を詰めて、配送業者さんに集荷に来てもらって送るだけ。
後日、「査定結果が〇〇円になりました」とメールや電話が来て、OKなら銀行口座に入金されます。
「日中は仕事で忙しくて、出張買取の立ち会いができない」とか「近所に楽器屋がない」という人には、めちゃくちゃ便利ですよね。
唯一のデメリットは、梱包作業がちょっと面倒くさい、ってことくらいでしょうか。
・持ち込み買取
これは、その名の通り、自分で楽器をお店(業者の拠点)まで持っていく方法です。
目の前で査定してもらって、金額にOKすれば、その場で「はい、じゃあ〇〇円ですね」と現金を受け取れることが多いです。
メリットは、この「スピード感」。
「今すぐお金が必要!」みたいな時には強いですね。
デメリットは、もうお分かりの通り、「運ぶ手間」が100%自分にかかること。
車を持っていて、業者の店舗が家から近い、という人向けの選択肢かな、と思います。
失敗しない!買取業者の選び方5つのポイント
さあ、3つの方法がわかりました。
じゃあ、次は「どの『業者』に頼むか」です。
ここが一番、本当に一番大事なところ。
「どこで売っても同じでしょ」なんて思ってると、大損しますよ。
私がいつもチェックしている「優良業者」を見極めるための5つのポイントを、こっそりお教えします。
ポイント1:楽器専門の査定士がいるか
はい、これ、最重要項目です。
絶対に「なんでも買います!」系の、総合リサイクルショップに楽器を持って行かないでください。
(※もちろん、ダメ元で値段を聞くのは自由ですが…)
なぜなら、彼らには「楽器の本当の価値」がわからないから。
ギターを見ても、「あー、ギターね。キズあるし、500円ね」みたいな、マニュアル通りの悲しい査定をされて終わる可能性が非常に高いです。
そうじゃなくて、「楽器買取専門店」を選ぶんです。
専門店には、楽器の知識が豊富な「専門の査定士」がいます。
その人は、あなたが持ってきた楽器のメーカー名、型番、製造年、状態を見て、「あ、これは〇〇年代の人気のモデルだから、このキズがあっても〇〇円の価値がありますね」と、ちゃんと「価値」を判断してくれるんです。
この差は、天と地ほどあります。
せっかく大切にしてきた(かもしれない)楽器を売るなら、価値がわかる人に見てもらう。これが鉄則ですね。
ポイント2:買取実績や口コミ・評判は良いか
「楽器専門店」と名乗っていても、本当に信頼できるかは別問題です。
そこで、次にチェックするのが「実績」と「口コミ」です。
まずは、その業者のホームページをじっくり見てみましょう。
「今月の買取実績」とか「買取事例」みたいなページはありませんか?
そこに、自分の楽器と似たようなものが、いくらぐらいで買い取られているか、情報が載っていることがあります。
「お、この店、ちゃんとギブソン買い取ってるな」とか「ドラムセットの買取例もある!」みたいに、実績が豊富なら安心感がありますよね。
あとは、Googleマップでそのお店の名前を検索したり、SNSで検索したりして、「リアルな評判」をチェックします。
もちろん、どんな人気店でも悪い口コミがゼロってことはないです。
でも、「査定が早くて助かった」「思ったより全然高い値段がついた」みたいなポジティブな声が多ければ、信頼できる可能性が高いです。
逆に、「査定額が低すぎる」「電話がしつこい」みたいな声が目立つところは、ちょっと避けた方が無難かもしれません。
ポイント3:手数料(送料・出張費・査定料)は無料か
これは、もう「当たり前」の基準になりつつあります。
今どきの、まともな楽器買取業者は、買取にかかる余計な手数料を「ぜんぶ無料」にしているところがほとんどです。
具体的には、
・宅配買取で楽器を送る時の「送料」
・出張買取で家まで来てもらう「出張費」
・楽器を見てもらう「査定料」
これらです。
「査定は無料です」と言っておきながら、「やっぱり売るのをやめます」と言ったら、「じゃあ、返送の送料はお客様負担で」とか「出張費だけはいただきます」とか言ってくるセコい(失礼!)業者も、残念ながら存在します。
お金をもらうために売ろうとしてるのに、逆にお金を取られたら、本末転倒じゃないですか(笑)。
「送料・出張費・査定料・キャンセル料、すべて無料」をうたっている業者を選ぶのが、絶対条件ですね。
ポイント4:キャンセル時の対応は明確か
手数料無料の話ともかぶりますが、これ、メンタル的にすごく大事です。
「査定金額が出たけど、正直、納得いかない…」
そんな時、ちゃんと「NO(売りません)」と言えるかどうか。
出張買取で家に来てもらって、目の前で査定されたら、なんだか断りにくい雰囲気になっちゃうこと、ありますよね。
そこで「あ、そうですか。じゃあ今回は見送ります」と伝えた時に、「そうですか、残念です。またお願いしますー」と、手数料なども一切請求せずに、スッと帰ってくれるかどうか。
宅配買取で送った後に、「やっぱり売るのやめます」と伝えた時に、「かしこまりました。送料無料で返送しますね」と言ってくれるかどうか。
この「キャンセル(売らない)の自由」が、ちゃんと保証されている業者を選びましょう。
金額に納得できないまま、「せっかく来てもらったし…」みたいなプレッシャーで売ってしまうのが、一番の後悔になりますからね。
ポイント5:自分の楽器のジャンルに強いか
これは、最後のひと押し、ちょっと上級者向けの視点です。
楽器買取専門店と一口に言っても、実は業者ごとに「得意ジャンル」が微妙にあったりします。
フェンダーやギブソン、マーチンといった、王道のエレキギターやアコギにめちゃくちゃ強いお店。
サックス、フルート、トランペットなどの「管楽器」の査定に自信があるお店。
マニアックなシンセサイザーや、DJ機材(ターンテーブルとか)の価値がわかるお店。
バイオリンやチェロなどの「弦楽器」専門のお店。
もし、あなたがすごくマニアックな楽器や、何十万円もするような高級なヴィンテージ品を持っているなら、そのジャンルに強そうな専門店に狙いを定めて査定を出すと、思わぬ高値がつくかもしれません。
まあ、そこまでじゃない一般的なギターやベース、キーボードなら、大手の楽器専門店さんなら、どこでもしっかり見てくれるとは思いますけどね。
少しでも高く売るためのコツ(掃除・付属品)
どうせ売るなら、100円でも高く売りたい。
それが人情ですよね。
査定額がちょっとアップするかもしれない、誰でもできる簡単なコツを伝授します。
1. とにかくキレイにする!
もう、これは基本中の基本ですが、効果はあります。
ホコリまみれの楽器と、ピカピカに磨かれた楽器。
あなたが査定士なら、どっちに高い値段をつけたいですか?
査定士も人間です(笑)。
ボディの指紋をクロスで拭き取ったり、指板の汚れをレモンオイルで軽く拭いたり、金属パーツを磨いたり。
「この人、大切に使ってたんだな」と伝われば、査定もちょっと甘くなるかもしれません。
2. 付属品は「すべて」揃える!
購入した時に付いてきたものは、押入れやクローゼットの奥から、全部引っ張り出してきましょう。
・説明書、保証書(期限が切れててもOK!)
・専用のソフトケース、ハードケース
・アンプの電源ケーブル、フットスイッチ
・ギターのトレモロアーム、調整用のレンチ類
・エフェクターの「元箱」
特に「元箱」と「専用ハードケース」、そして「説明書」あたりは、あるとないとで査定額がはっきり変わることも多いです。
「こんなもの、いらないだろ」と思わずに、全部まとめて査定に出しましょう。
査定前に型番やメーカー名を調べておこう
これは、高く売るコツというより、査定をスムーズに進めるためのコツですね。
買取を申し込むとき、電話でもWebフォームでも、必ず「メーカー名」と「型番(モデル名)」を聞かれます。
その時に、「えーっと、たしかフェンダーの、赤いギターで…」みたいになると、査定士さんも「うーん、それじゃ値段が出せませんね…」となってしまいます(笑)。
・ギターなら、ヘッド(先端)に書いてあるロゴ(FenderとかGibsonとか)と、モデル名(Stratocasterとか)
・アコースティックギターなら、サウンドホール(丸い穴)の中を覗くと、ラベルが貼ってあります
・キーボードやアンプなら、本体の裏側や背面にシールが貼ってあり、そこに「Roland JUNO-DS61」みたいに書いてあります
これを事前に調べてメモしておくだけで、申し込みがめちゃくちゃスムーズに進みます。
「ああ、あのモデルですね。状態が良ければ〇〇円くらいですよ」と、話が早いんです。
「このお客さん、ちゃんとわかってるな」と思わせることで、足元を見られる(安く買い叩かれる)のを防ぐ、という地味な効果もあるかもしれませんよ。
まとめ:楽器の処分は「捨てる」より「売る」を検討しよう
いやー、お疲れ様でした。
かなり長い内容になってしまいましたが、最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。
ここでは、「楽器を捨てたい」と思った時に知っておくべき、廃棄のリアルな手順とコストについて、かなり詳しく掘り下げてきました。
どうでしょう?
「楽器を捨てる」って、私たちが思っている以上に、
・お金(手数料)がかかる
・手続きや搬出が、めちゃくちゃ面倒くさい
・「もったいないな…」という罪悪感が残る
…ということが、お分かりいただけたかと思います。
まさに、記事のタイトル通り「『捨てる』は損!」なんですよね。
一方で、その「損」をすべて「得」に変えてしまう魔法のような選択肢。
それが「楽器買取りサービスを利用する」=「売る」という方法でした。
・廃棄費用(マイナス)が「ゼロ」になるどころか…
・臨時収入(プラス)がもらえるかもしれない
・面倒な搬出や手続きも、ぜんぶ「お任せ」できる
・次の誰かに使ってもらえて、罪悪感も「ゼロ」
もう、これを選ばない理由がないんじゃないかな?と、個人的には強く思います。
この記事を読んでいただいたあなたには、部屋の隅でホコリをかぶっている楽器を見て、「あ、あれ捨てなきゃ…(面倒だなあ)」と思うのではなく、「あ、あれ、いくらになるか聞いてみようかな」と、ちょっとワクワクする行動に移してもらえたら、すごく嬉しいです。
何度も言いますが、「こんな古いの、壊れてるの、売れるわけない」と、あなたが自己判断してしまうのが、一番もったいないですからね。
今の時代、プロの査定士さんに見てもらうのは「タダ(無料)」なんです。
ダメ元で聞いてみて、もし値段がついたらラッキー。
値段がつかなくても、損はしないわけですから。
あなたの楽器が、粗大ごみとして悲しく処分されるんじゃなく、次の持ち主さんの元で、また素敵な音を奏でてくれる。
そんなハッピーな選択を、ぜひ検討してみてくださいね。
あわせて読みたい!楽器の処分に関する関連記事
さて、この記事では「楽器を捨てる(廃棄する)」場合の方法と、「買取サービスで売る」方法の2つを、かなり詳しく比較してきました。
でも、楽器を手放す方法って、実はこれだけじゃないんですよね。
「そもそも、どんな選択肢があるのか全体像を知りたい!」という方もいるかもしれません。
そんな方は、まずは楽器の処分方法を5つに整理した、こちらの記事を読んでみるのがおすすめです。
自分にどの方法が合っているか、比較検討できますよ。
→ 使わなくなった楽器、どうしてる?賢い処分方法5選(買取・下取り・寄付・廃棄)
また、「お金にする(売る)」ことにはあまり興味がないけれど、「捨てるのは忍びない…」という、心優しいあなたもいると思います。
そんな時は、「寄付」や「譲渡」という選択肢もありますよ。
あなたの楽器が、どこかで社会貢献に役立つかもしれません。
詳しい手続きやメリット・デメリットはこちらにまとめています。
→ 楽器を寄付・譲渡する方法とメリット・デメリット【社会貢献】
「今度、新しい楽器を買う予定があるんだよね」という方もいますよね。
その場合、お店で「下取り」してもらうのと、今回紹介した「買取」に出すの、どっちがお得なの?と迷うかもしれません。
はい、それ、めちゃくちゃ大事なポイントです。
「下取り」と「買取」の違いを徹底的に比較した記事がこちらです。
最後に、今回の悩みは「自分の楽器」ではなく、「実家に置きっぱなしの古い楽器」や「親の遺品整理」で困っている、というケース。
これはまた、ちょっと事情が違ってきますよね。
誰のものかわからない楽器をどう扱えばいいのか、そのコツをまとめた記事もあります。
→ 実家の古い楽器はどう処分する?親の遺品整理・片付けのコツ
あなたの今の状況や、楽器への思いにピッタリ合う記事が、この中にあるかもしれません。
ぜひあわせてチェックしてみて、後悔のない「楽器の処分」を選んでくださいね。